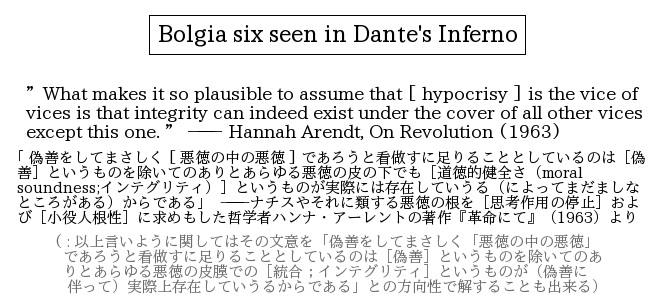ダンテ『地獄篇』とミルトン『失楽園』に見る(「今日的観点で見た場合の」)ブラックホール近似物に関して何が問題になるのかについて ――『ギルガメシュ叙事詩』を引き合いにして純・記号論的に述べられもすること[4]
直前にあってはミルトン『失楽園』について何を述べてきたかにつき(そうしたことを筆者が取り上げた問題意識が奈辺にあるのか示しもしつつ)振り返りもし、次いで、ダンテ古典やミルトン古典の相互に関連する特定部の奇怪なる描写について言及なしはじめる「その前に」本稿にてどういったことの指し示しに注力なしてきたかについての振り返りをなした。 そちら長くもなっての振り返り部の内容を前提に話を進める。
さて、これ以降の段では
[何故、ミルトン『失楽園』の特定部描写(アビスを横断しての罪と死の通用路の確立にまつわる描写)が[トロイア崩壊]のみならず(ミルトンが目にすることはできなかったはずの)『ギルガメシュ叙事詩』とも結びつきもすると述べられるのか、また、そのことが何故、問題になるのかについてのさらに突き進んでの話]
をなすこととする。
本稿の先立っての段では
「エデンの園で蛇(に変じてのサタンともされる存在)がアダムとイヴより[不死を奪った]との見方が出来るとのこと、そして、それがギルガメシュ叙事詩(のウトナピシュテムの洪水伝承にまつわる部)で蛇がギルガメシュより[不死を奪った]パートとの接合性を観念できるところとなっている」
とのことを解説なしもした(:一致性の機微を指摘するにあたっては『ギルガメシュ叙事詩』にまつわる専門の学者による叙事詩解説媒体よりの引用をなし、また、エデンの園での誘惑ありようについて論じた識者媒体よりの引用をなし( Project Gutenbergにて公開されている19世紀末の書籍から引用をなし)、同じくものこと、解説していた)。
他面、本稿ではよりもって先立つところにて、
「[黄金の林檎がやりとりされ、トロイア崩壊の原因になったパリスの審判]と[禁断の果実が誘惑の具とされたエデンの園の誘惑]には尋常ならざる接合性が見てとれる」
とのことを(属人的主観が問題になるようなことではなくにも、の)記号論的多重的一致性に関わるところとして指摘しもしていた(:そちら[黄金の林檎を巡るパリスの審判と禁断の果実を巡るエデンの誘惑の一致性]についてはほんのつい先程の段でもくどくもの従前内容の振り返り表記をなしているところである)。
上のことらは ――「ここまでの内容のみを顧慮するのならば」だが―― 次のような問題性を帯びていると批判されようもの「でも」ある。
i.「(蛇による不死の略取との側面が介在していても)[ギルガメシュ叙事詩]と[エデンからの追放の物語]はそれら全体が密接につながっているわけではない。であるから、両者の一部類似性を過度にピックアップして立論展開をなすのは良心的なやりようではない」
ii.「[パリスの審判]と[エデンの園]の誘惑の方は確かに複合的なる接合性を呈しているようだが、ただし、パリスの審判での林檎が[誘惑者の取得目標物]であったのに対して、エデンの園の誘惑にての禁断の果実(林檎とも見られることがある果実)は[誘惑の具]となっているものである。[目標]と[手段]との差異があるところで同一性を問題視するのもどうかととれるところである」
以上のようなかたちで呈されうる批判的見地の存立根拠を無効化し、かつ、
[『ギルガメシュ叙事詩』から(黄金の林檎にて滅んだトロイアと悪魔の誘惑が濃厚に結びつけられている古典である)ミルトン『失楽園』に至るまでの多くのことが[黄金の林檎](およびヘラクレスの11功業)に結合するようになっている]
ことを示すべくもの指摘をこれよりなしていくこととする。
ここで申し述べるが、直上呈示の、
ii.「[パリスの審判]と[エデンの園]の誘惑の方は確かに複合的なる接合性を呈しているようだが、ただし、パリスの審判での林檎が[誘惑者の取得目標物]であったのに対して、エデンの園の誘惑にての禁断の果実(林檎とも見られることがある果実)は[誘惑の具]となっているものである。[目標]と[手段]との差異があるところで同一性を問題視するのもどうかととれるところである」
との批判的見立てに対しては次のようなことが[再反論]として述べられる。
「本稿にて[際立っての要素]を持つ代表的古典として問題視しているミルトン『失楽園』ではサタンが[林檎]としての誘惑の果実(知恵の樹の実)で人間を堕落させたと描写されるわけだが、そのやりようを罰するとのかたちで神がサタンらをして[林檎の中毒者]に仕立て上げたと描写されて「も」いることがある。すなわち、堕地獄を見たサタン(ルシファー)を長と戴く堕天使らは[林檎を用いての人類の始祖の堕落促進]の罪過を問われるかたちにて[林檎(知恵の樹の実)なくして生きて行けぬ身体]に神にされたなどと『失楽園』という古典には描写されているとのことがある ―直下にての原文抜粋部を参照のこと― (:知恵の樹の実、フォゥビドン・フルーツが林檎であるとの表記すら見当たらない聖書本文とは無縁なるそのようなアレンジ ―知恵の樹を用いて誘惑をなした者が知恵の樹の実の中毒者に罪過として仕立て上げられたなどというアレンジ― がどうしてキリスト教文学の金字塔などと称されてきた『失楽園』にてなされているのか、そう、[何故なのか]の問題は置き、とにかくもそういう描写がなされているとのことがある)。
林檎は[誘惑の具]であるのと同時に悪魔らにとり[神に強いられての渇望の元]にも変じていると『失楽園』で描かれているわけであるが、それはパリスの審判にて([明けの明星]ルシファーよろしく金星と結びつく)アフロディテが黄金の林檎を是が非でも取得しようとしていたと描写されていること、また、(後述するところとして)北欧神話にて[黄金の林檎]が神々に不死を約束するためのなくてはならぬ常食とされていたことと話が接合するところである」
直上にて言及なしたこと、[林檎が[堕天使]変じての[悪魔]らの常食と化したとイングランドの代表的古典であるジョン・ミルトン『失楽園』にて描写されている]とのことにつき、原典の記述を引いておくこととする。
(以下、『失楽園』にて[蛇に変じての林檎による誘惑]を奏功させたサタンことルシファーが仲間に演説をなし、その後どうなったのかとのことにまつわる記述を岩波文庫版『失楽園』(平井正穂訳)にあっての原著第10巻の部を納めたパート(P.182-p.187)より ――出典(Source)紹介の部54(2)の部にて既に抜粋なしていたところから再度の引用をなすとのかたちで―― 引くこととする)
そこでわたしは陰謀をめぐらしてその人間を誘惑し、創造主(つくりぬし)から引き離してやった。――しかも、驚くことなかれ、そのために用いたのは、僅か、一個の林檎にすぎなかったのだ!そして、笑うことなかれ、それを怒った創造主(つくりぬし)、自分の愛する人間とそのすべての世界を悉く『罪』と『死』の餌食として、われわれの餌食として、抛(ほう)り出してしまったのだ!
・・・(中略)・・・
いかにも神はわたしをも裁いた、というより、わたしのかわりに、わたしが人間を騙した際に姿を借りたあの動物、つまり蛇だ、あれを裁いたというわけだ。
・・・(中略)・・・
そう言ったあと、恐らく自分の耳を聾(ろう)するばかりの講堂の喝采と称賛の声が忽(たちま)ちあがるものと思い、期待に胸をふくらませ、暫時佇立(ちょりつ)していた。ところが意外にも、四方八方から彼の耳を襲ってきたものは、無数の舌、舌、舌から漏れてくる不気味なしゅっしゅっという声であった!どうしたことか、と異様さに驚いたが、次の瞬間、こんどは自分自身の異様の変化にさらに驚いた。
・・・(中略)・・・
そこには腹這いになったまま必死に、だが空しく、もがいている一匹の巨大な蛇の姿があった。より大いなる力が今彼を圧倒し、裁きに従って、彼が罪を犯した当時の姿にその姿を変えて、彼が罪を罰したのだ。
・・・(中略)・・・
彼の大胆不敵な叛乱の共犯者として、誰も彼も同じように蛇に姿を変えられてしまっていた。大広間のあちらこちらから発せられるしゅっしゅっという声は、凄絶な響きをあげていた。あらゆる所で、頭と尾が絡み合った怪物の群れがのたうちまわっていた。蠍(さそり)や毒蛇や恐ろしい両頭蛇(アンピスバイナ)や角蛇(ケラスケス)や水蛇(ヒドロス)や海蛇(エロツプス)や飢渇蛇がそこにいた(ゴルゴンの血が滴り落ちた例の土地でも、蛇島(オフユーザ)でも、これほど多数の蛇が蝟集し蠢いたことはかつてなかった)。しかし、やはりなんといっても、その中で最も巨大だったのは、今や巨竜(ドラゴン)に変じていたサタンであった。彼は、かつて太陽の熱によってピュートの谷間の泥の内に生じた、あの巨大な錦蛇(ピュトン)よりも、さらに巨大であった。大きさの点に劣らず、力もまた依然として儕輩(せいはい)を凌(しの)ぐものを保持している様子であった。
・・・(中略)・・・
警備のために、或(あるい)は閲兵をうけんものと、意気軒昂として整列し自分たちの栄ある首領が颯爽として出てくるのを、この目で見ようと息をのんで待っていた。やがて彼らは見た、――だが全く意外な光景であった!それはぞろぞろと這いながら出てくる醜悪な蛇の大群だったのだ。
・・・(中略)・・・
同じように次々に彼らに感染していった。
・・・(中略)・・・
この彼らの変身と時を同じくして、突如としてすぐ近くの地中から森が一つ姿を現していた。これこそ彼らに対する懲罰をいっそう厳しくしようとする神の御意志(みむね)から出たものであった。そこには美しい果実が、あの誘惑者サタンがイーヴを惑わす際に好餌(こうじ)として用いた、楽園(パラダイス)の例の果実そっくりの美しい果実が、たわわに実っていた。この異様な光景を見て、こんな風にあの一本の禁断の樹のかわりに夥(おびただ)しい禁断の樹が生じたのは、もしかしたら自分たちをいっそう苦しめ辱めるためかもしれぬ、と想いながら、彼らはまじまじとそれを凝視していた。だが、焼けつくような渇きと激しい飢えとに苛まれ、この果物が自分達を欺くために送られたかもしれぬとは思いつつも、どうにも我慢出来なくなり、続々と這い上がり樹によじ登った。
・・・(中略)・・・
何度も何度も食べようとした。そのつど吐気を覚え、どうにも我慢できぬ味の悪さに辟易して、口じゅう煤と灰だらけになったその顎(あぎと)を歪めるだけであった。こんな風にして彼らは何度も同じ迷妄に陥った。そこが、彼らに征服されて一度だけ過ちを犯した人間とは違うところであった。
・・・(中略)・・・
やがて神に許されて ・・・(中略)・・・ 或る日数に限ってこのような恥ずべき蛇の姿に身を窶(やつ)すことを彼らに命じ給うたという
(国内で流通を見ている訳書よりの引用部はここまでとする ―※― )
(※尚、ここにて引用の訳書記述に該当する原著表記はオンライン上より確認可能となっており、その部についての引用もなしておくこととする(疑念疑義があるとの向きにして、かつ、見識あるとの向きにあって[文献的事実]か否かの問題につき確認いただきたくも原著よりの引用をなしておく)。それでは、以下、
Henry Walshとの人物を編者として著名な挿絵家 Gustave Doreの手になる挿絵が付されているとの Internet Archive公開版あるいは Project Gutenberg公開版(それぞれ確認する気があるのならば全文ダウンロードできもしようとの版)の PARADISE LOST原著にての BOOK X.より引用なすこととする。
→
Made happy. Him by fraud I have seduced / From his Creator; and, the more to increase / Your wonder, with an apple. He, thereat / Offended worth your laughter hath given up / Both his beloved Man and all this world, / To Sin and Death a prey, and so to us, / [ . . . ] / True is, me also he hath judged, or rather / Me not, but
the brute serpent, in whose shape / Man I deceived. / [ . . . ] / So having
said, awhile he stood, expecting / Their universal shout, and high applause, / To fill his ear; when, contrary,
he hears, / On all sides, from innumerable tongues, / A dismal universal
hiss, the sound / Of public scorn. He wondered, but not long / Had leisure,
wondering at himself now more. / His visage drawn he felt to sharp and
spare, / His arms clung to his ribs, his legs entwining / Each other, till,
supplanted, down he fell / A monstrous serpent, on his belly prone, / Reluctant,
but in vain ; a greater Power / Now ruled him, punished in the shape he
sinned, / [ . . . ] / Alike, to serpents all, as accessories / To his bold riot.
Dreadful was the din / Of hissing through the hall, thick-swarming now
/ With complicated monsters, head and tail, / Scorpion, and Asp, and Amphisbaena
dire, / Cerastes horned, Hydrus, and Ellops drear, / And Dipsas not so
thick swarmed once the soil / Bedropt with blood of Gorgon, or the isle
/ Ophiusa-but still greatest he the midst, / Now Dragon grown, larger than whom the sun / Engendered in the Pythian
vale on slime, / Huge Python, and his power no less he seemed / [ . . . ] / Sublime with expectation when to see / In triumph issuing
forth their glorious chief. / They saw, but other sight instead - a crowd
/ Of ugly serpents! Horror on them fell, / And horrid sympathy for, what
they saw, / They felt themselves now changing. / [ . . . ] / Cast on themselves
from their own mouths. / There stood / A grove hard by, sprung up with this their change, / His
will who reigns above, to aggravate / Their penance, laden with fair fruit,
like that / Which grew in Paradise, the bait of Eve / Used by the tempter. On that prospect strange / Their earnest eyes they
fixed, imagining / For one forbidden tree a multitude / Now risen, to work
them further woe or shame. / Yet, parched with scalding thirst and hunger fierce, / Though to delude
them sent, could not abstain ; / But on they rolled in heaps, and up the
trees / Climbing, sat thicker than the snaky locks / [ . . . ] / Their appetite with gust, instead of fruit / Chewed bitter ashes, which the offended taste / With spattering noise rejected. Oft they assayed, / Hunger and thirst constraining; drugged as oft, / With hatefulest disrelish writhed their jaws, / With soot and cinders filled; so oft they fell / Into the same illusion, not as Man / Whom they triumphed once lapsed. [ . . . ] / Thus were they plagued, / And worn with famine, long and
ceaseless hiss, / Till their lost shape, permitted, they resumed, / Yearly
enjoined, some say, to undergo / This annual humbling, certain numbered
days, / To dash their pride, and joy for man seduced.
(オンライン上より確認可能な原著よりの引用部はここまでとする/ちなみに『失楽園』は叙事詩形態の著作として頻繁に改行がなされている作品ともなるわけだが、そちら改行部についてはスラッシュで表した))
上にての引用なしての部、そこにては
「中途半端なかたちでしか知恵の樹の実を味わっていない人間に比べて十二分に知恵の樹を味わっている自分達は同時に知の苦さも知っている」
とのかたちでの相応の存在の見立てを代弁しているようにもとれる側面があると本稿筆者などは穿(うが)っている ――それは植民地運営機構(あるいはナチスの絶滅収容所のような収容所ないし[畜舎]の運営機構とした方が適切か)の係官が手ずから押しつけた荒唐無稽宗教、カーゴ・カルトが如きものを奉じている[知]の欠如を見た操作対象種族、自分達の薬籠中にしているとの我々人間を馬鹿にしながらも発している[戯言]のようなものともとれる―― のだが、とにかくも、ミルトン古典『失楽園』(のサタンがアビスを横断して[罪と死が押し通る通用路]を構築するとの部)には
「天使の姿を保っていたものの、一時的に蛇に変じて人間を騙した神への叛乱者サタンは」
「人間を林檎によって罪と死の餌食にしたとのことを仲間に誇る ―結果的に神がそうした結果を追認することになったとのことで誇る― ための演説をなそうとした瞬間に」
「同類の仲間の反逆堕天使ら共々、エデンでの蛇に変身しての誘惑を咎めるかたちにて爬虫類の類に変じさせられ」
「そのうえで人間を騙したのに用いた林檎(知恵を約束する禁断の果実)を口に苦いものとしてながらそれに依存するような立ち位置へと神によって追い込まれた」
との記述が ――直上引用部にあって見てとれるように―― [文献的事実]として認められるわけである。
[天使らと悪魔らの古典上の図像化形式について]
ミルトンの描くサタンことルシファーは人間を林檎で騙すことに成功するまで([神に歯向かって地獄に落とされた堕天使]とはいえ)[天使であった頃の似姿をある程度、保持している]ようにも描かれているとのことがある。
たとえば、ギュスターブ・ドレ、19世紀にて著名だった同挿絵家がミルトン『失楽園』の近代刊行版に付した挿絵で描かれるサタンの姿がどれも「翼こそ蝙蝠のようなものに代えて描写されている」とはいえ天使に近しき姿で描かれているとのことがある、そういったことよりも確認できるところとして、である(オンライン上より容易に確認できるとのところだが、ギュスターブ・ドレ作品群については下にもその一部を呈示しておく)。

上掲図にあっての上の段は
[ミルトン『失楽園』の近代刊行版にて著名な芸術家ギュスターブ・ドレ( Gustave Doré )が提供した挿絵らを挙げているとの部]
となり、そこにて呈示の画らはそれぞれ
[サタン(ルシファー)が叛逆天使として天より放逐される場面を描いている画] (左上)
[サタン(ルシファー)が天使然とした姿にて(ローマの万神殿パンテオンのもじりとしてミルトンによって生み出された造語として知られるとの)[地獄の万魔殿;パンデモニウム]で共に堕天した堕天使らに対する演説をなしている場面を描いた画] (右上)
[サタン(ルシファー)が人間の堕落のためにエデンに向けて単身飛行をなした先にて蛇の姿を目に留める場面を描いている(と思しき)画](左下)
[サタン(ルシファー)が蛇に変じてアダムとイヴを誘惑する場面を描いている(と思しき)画] (右下)
となる。
ミルトン失楽園に見るサタンはそれらのギュスターブ・ドレ挿絵に見るように天使然とした存在から次第次第にステレオタイプ然とした古き蛇、悪魔としての特性を帯びてゆくさまが描写されるとの存在である(:最終的に同サタンは同輩の堕天使らが蛇、爬虫類の怪物に変化させられる中、人間を堕落させたとの行為の代償に[巨大な竜]に変じさせられたと描写される ――直近の段にてその下りは原文引用なしているとおりである―― )。
対して、上掲図にあっての下の段では
[19世紀アカデミズム絵画の巨匠の一人として知られるウィリアム・アドルフ・ブーグロー( William-Adolphe Bouguereau )が描いた天使らをモチーフにしての画] (下段左)
および
[(「意味深い」と筆者が受け取っていることに)ミルトン『失楽園』近代刊行版と並んでダンテ『地獄篇』近代刊行版に「も」挿絵を提供していたとの画家ギュスターブ・ドレがダンテ『地獄篇』にあっての[地獄の獄卒(監視兼拷問役)の悪魔ら似姿]を描きだした画] (下段右)
を挙げもした。
以上の図像らに視覚的に見てとれる、
[天使らが変じての悪魔ら]
との設定。
そこから両者[天使][悪魔]が「表裏」一体の存在である ―神学(セオロジー)に見る堕天使が悪魔であるといった観点を特段顧慮せずとも元来からして一体の存在である― との見立てが強くもなせると筆者はとらえている(要らぬところながら属人的目分量につき言及すれば、偽善・まやかしだらけの世界にあって殊に欺瞞性が色濃くも現われているとの[宗教]の領域に関することとしては「相応しい特性であろう」とも筆者はそれにつきとらえもしている)。
ここで
ii.「[パリスの審判]と[エデンの園]の誘惑の方は確かに複合的なる接合性を呈しているようだが、ただし、パリスの審判での林檎が[誘惑者の取得目標物]であったのに対して、エデンの園の誘惑にての禁断の果実(林檎とも見られることがある果実)は[誘惑の具]となっているものである。[目標]と[手段]との差異があるところで同一性を問題視するのもどうかととれるところである」
とのありうべき申しように対するところとして筆者より応じて呈示したいとしたこと、
「本稿にて[際立っての要素]を持つ代表的古典として問題視しているミルトン『失楽園』ではサタンが林檎としての誘惑の果実(知恵の樹の実)で人間を堕落させたと描写されるわけだが、そのやりようを罰するとのかたちで神がサタンらをして[林檎への依存者]に仕立て上げたと描写されて「も」いることがある。すなわち、堕地獄を見たサタン(ルシファー)を長と戴く堕天使らは[林檎(知恵の樹の実)]なくして生きて行けぬ身体に神にされたなどと描写されているとのことがある(聖書には見られないとのそのようなアレンジがどうしてなされているのか、そう、[何故なのか]の問題は置き、とにかくもそういう描写がなされているとのことがある)。
林檎は誘惑の具であるのと同時に悪魔らにとり[神に強いられての(常態的なといった式での)渇望の対象]にも変じていると『失楽園』で描かれているわけであるが、それはパリスの審判にて([明けの明星]ルシファーよろしく金星と結びつく)アフロディテが黄金の林檎を是が非でも取得しようとしていたと描写されていること、また、(後述するところとして)北欧神話にて[黄金の林檎]が神々に不死を約束するためのなくてはならぬ常食とされていたことと話が接合するところである」
にあっての
「北欧神話にて[黄金の林檎]が神々に不死を約束するためのなくてはならぬ常食とされていたことと話が接合するところである」
との部についての解説を講じておくこととする。
ミルトンの『失楽園』にあっては、(先にての抜粋部に見るように)、[天使より爬虫類の妖異らに変じた者達](サタンら堕地獄の堕天使の面々)もまたエデンの誘惑を咎としての追罰を科せられるかたちにて
[「知恵の実たる林檎」に骨まで依存しきっての状況に陥った]
と記されているわけだが、北欧神話では[黄金の林檎]は欠かすことの出来ぬ[(多神教の)神々の常食]と描写されている。
につき、リヒャルト・ワグナー戯曲、 Der Ring Des Nibelungen、英語ではただ単純に The Ring[リング]とだけ呼称されること多い同『ニーベルングの指輪』(の中の[ラインの黄金]の部)にあっては
[[黄金の林檎]が[神々がそれに依存しきり[常食]とする不死を約束する食べ物]として描写されている]
とのことがよく知られているとのことがある (:たとえば、リヒャルト・ワグナー『ニーベルングの指輪』については、である。オンライン上から容易に確認できるところとして和文ウィキペディア[ラインの黄金]項目にあって「現行にて」(一文のみの引用なして)フライアの作る若返りのリンゴが食べられなくなった神々は若さを失い始める。意を決したヴォータンは、ラインの黄金を手に入れるためにローゲを伴って地下に降りてゆく
と記載され(注:ワグナー叙事詩ではフライヤFreiaだが、現実の北欧神話ではイドゥンIðunnという女神が同じくもの役割を担う)、英文Wikipedia[ Das Rheingold ]項目にて(全くもって同じところとして)現行にて Freia's golden apples had kept the Gods eternally young; in her absence, they begin to age and weaken. In order to win Freia back, Wotan resolves to follow Loge down into the
earth, in pursuit of the gold
.と記載されているとおりである)。
黄金の林檎 ――本稿の先立っての段にてエデンの果実との接合性を入念に解説してきたとの伝説上の果実―― については北欧神話ではギリシャ神話における[アンブロシア](不死を約束するギリシャ神話の神々の食物)と同等のものとしての設定が付されてもいるわけである。
補足表記の部
補足表記として[1]
北欧神話にあって神々が[黄金の林檎]としての[若返りの林檎]を常食としているとされている(和文ウィキペディア[黄金の林檎]項目程度のものにも、引用なせば、北欧神話では、黄金の林檎は神の不老不死の源とされる。これはギリシア神話におけるアムブロシアーに当たる。女神イズンが林檎の管理に当たっており、林檎と最も関連付けられる
(引用部はここまでとする)と記載・解説されているようなところである)ことについてであるが、その黄金の林檎、ときにワグナー(『ニーベルングの指輪』こと The Ringを生み出したリヒャルト・ワグナー)のオペラ『リング』ならぬところでも[リング]と結びつけられるようなもの「でも」ある。
その点、[「円形」加速器]としての巨大なリング、ラージ・ハドロン・コライダー(本稿にてその特質を専らに問題視しているとのブラックホール生成をなしうるとされてきた装置でリヒャルト・ワグナーならぬウォルター・ワグナーのような人物にブラックホール生成の可能性が目立って問題視されだした(本稿前半部にて解説を講じている訴訟に関わるところで目立って問題視されだした)との装置)がそのような構造をとる[リング]と[黄金の林檎]の結びつきにつき述べれば、例えば、次のようなことがある。

ここ出典(Source)紹介の部60(3)にあっては
[北欧神話にての一部エピソードが[黄金の林檎]と(リヒャルト・ワーグナーの近代歌劇の内容を想起させるような)[魔法の指輪]を結びつけているものとなっている]
ことにまつわる出典を挙げおくこととする。
(直下、 Project Gutenbergより誰でも入手できるとのH. A. Guerberという前世紀前半まで活動の英国人史家の手になる Myths of the Norsemen From the Eddas and Sagas(『エッダからサガに至るまでの北欧人種の神話』とでも訳せよう著作)にての The Wooing of Gerdaとの節に見る『スキールニルの歌』というエッダ収録詩に対する解説部よりの引用をなすとして)

To induce the fair maiden to lend a favourable ear to his master’s proposals, Skirnir showed her the stolen portrait, and proffered the golden apples and magic ring, which, however, she haughtily refused to accept, declaring that her father had gold enough and to spare.
(補ってもの訳として)
「(スキールニルという男が自身が北欧の神フレイの恋の仲介役を演じることになったとのその相手方の巨人族の乙女ゲルズの説得に際し)輝く金髪の乙女の耳をば自分の主人の提案へと傾けさせるため、スキールニルは主人の肖像を見せ、そのうえで、[黄金の林檎]と[魔法のリング]を(彼女がフレイ神と結ばれる対価に、と)提示したが、彼女は[彼女の父は十分にして余りあるほどの黄金を持っている]とたからかに述べ、その申し出を容れることを拒んだ」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )
(※ちなみに上にて magic ring[魔法のリング]とされているのはDraupnirドラウプニルという固有名詞が与えられているものとなる。同ドラウプニルについては日本ではアームブレスレット(腕輪)と表されもすることがあるものだが、[オーディンの金の「リング」]であると表現されることが英語圏では多いものとなり、たとえば、英文Wikipedia[Draupnir]項目なぞには In Norse mythology, Draupnir is a gold ring possessed by the god Odin with the ability to multiply itself: Every ninth night eight new rings 'drip' from Draupnir, each one of the same size and weight as the original.[ . . . ] It was offered as a gift by Freyr's servant Skirnir in the wooing of Gerdr, which is described in the poem Skirnismal.
(訳として)「北欧神話における[ドラウプニル]とはオーディンに保有されている[増殖能力を帯びての黄金の「指輪」 a gold ring]となる。9夜毎に元となったものと同じサイズ・同じ重量の新たなドラウプニルがドラウプニルからドリップ、滴り落ちてくる・・・(中略)・・・同リングは『スキールニルの歌』にて表されるところ、ゲルズへの求婚に際してフレイ神の従僕スキールニルより贈り物として呈示されたものとなっていた」との記載が見受けられるところとなっている)
(出典(Source)紹介の部60(3)はここまでとする)
以上、引用元著作( Project Gutenbergにて公開されている Myths of the Norsemen From the Eddas and Sagas)に見るように、黄金の林檎は
[魔法の指輪]([腕輪]とされることもあるが、[指輪]とも表されるドラウプニル)
とセットとなるかたちにて[神の求婚に際しての贈答品](婚儀確約とはあいなっていないわけだから、結納の品とはここでは記さない)とされている、そう、北欧神話の[黄金の林檎]は[リング]と(ワグナー戯曲『ニーベルングの指輪』ことザ・リング以外のところでも)結びつけられるようなもの「とも」なっている。
補足表記として[2]
何故、そうした話をここで「敢えても」なすのか、よく慮(おもんぱか)っていただきたいのだが、
[ヴィデオテープに映し出された井戸から現われてヴィデオを見た人間達を時限爆弾よろしく一定期間経過後に正確に殺していく亡霊]
を登場させたことで「かなり有名な」日本の小説作品群としてリング・シリーズという作品がある(同リング・シリーズは邦画としての映画化のみならず[皆既日食]が印象深くも描かれてのハリウッド映画化版も世に出ている)。
「唐突な、」と当然に思われるところか、とも思うが、上にて言及したそちらリング・シリーズの一連の物語の結末を描いた続編作として
『ループ』(1998年初出/『リング』に同じくも作家の鈴木光司の手になる小説作品)
という作品が世に出されてもいる。
同『ループ』の中では
[リング・シリーズの中でテレビ画面(ヴィデオが再生されてのテレビ画面)から登場して被害者をくびり殺していく[貞子]という[怨霊]] (正確には[怨霊]と「されてきた」存在)
のやりように対して「そうきたか.」といった按配の[サイエンス・フィクション]的な説明が付されている。次のようなかたちにて、である。
→
[ヴィデオテープの中の井戸から立ち現れ、時限性の爆弾か何かのように正確にヴィデオテープを視た者を殺していくとの[貞子](ダヴィングされれば、複製分のヴィデオテープの数だけ「増殖」する存在でもある)が登場する世界は実は仮想現実世界、「リアル・ワールド」としてのアメリカで構築された仮想現実世界であった。 そのような世界だから[貞子]という存在が世界シュミレートに際してのバグ、増殖して破滅をきたす存在として仮想世界に産まれ落ちることになった ――(小説『リング』の世界では被害者も加害者も皆、仮想現実の中で生み出された実体なき存在であるなどとの話の展開を見るに至っている)―― ]。
上に見る仮想世界がどういう風にシュミレートされていたかだが、リング・シリーズ最終作の小説『ループ』の中では ――ほとんどディーテルに対する描写がない、それがゆえにテーマ性がかえって強くも感じられるとの式で――
[元々の巨大な加速器施設遺構の設備が利用されてのシュミレートがなされた仮想世界[ループ]]
こそが[井戸から登場する亡霊](の名を冠したシステムのバグ)が猛威を振るうことになったまさしくもの世界であるとの[設定]が導入されてもいる ――疑わしきにおかれては『ループ』(角川書店)を直に購入するなり借りるなりして確認してみるとよかろうが、当方の手元にある『ループ』(平成12年9月10日発行の「文庫」版)の[第二章ガン病棟]p.140からp.141より抜粋するところとして次のような記載がなされているところである。(以下、原文抜粋部とするとして)打って変わって、画面には広大なアメリカの砂漠地帯が映し出されてゆく。はるか以前に計画は中止され、使われなくなった直径五十キロにも及ぶ超伝導加速器の航空写真による外観から、その内部の模様を、カメラはとらえていた。無用の長物と化したリング状の巨大研究施設の内部には、膨大な数の超並列スーパーコンピューターが並んでいる。砂漠の地下に眠るコンピューターの数は実に六十四万台、まさに圧巻の光景であった。場面は突如、超高層ビルが林立する東京へと変わった。カメラは地下へと潜ってゆく。現在は使われなくなった地下鉄のトンネルが蜘蛛の巣のように張り巡らされた地下の迷宮・・・・・。そこにもまた六十四万台の超並列スーパーコンピューターが設置されている。一年を通して温度差が少なく、湿気も少ない地下という環境は、コンピューターを設置するのに最適である。日米合わせて百二十八万台という想像を絶する数の超並列スーパーコンピューター群が、『ループ』を支えるのだ
(抜粋部はここまでとする)とあるとおりである―― (加速器とくれば、(往々にして只のホラー小説に留まっていた段階の小説『リング』と通底する)[リング]状の形状を呈しているわけだが、その点からして、[恣意性]を感じさせもするところである)。
整理すれば、
[加速器設備の遺構(に据え置かれたコンピューター群)の中でシュミレートされた世界にあって[エラー]として産まれ落ちた存在、亡霊と呼ばれる貞子なる存在が(彼女が猛威を振るうことになった仮想現実世界の住人から見れば)[地に開いた穴(井戸)から現われて[人々に絶対死亡の状況を正確に与える時限性の殺人マシン]たる増殖性・拡散性を呈しての亡霊]としての姿を呈している]
との設定が採用されているわけである(普通に考えれば、どうしてそうした設定が出されたのか、不可思議にも思われもしようとの「設定」ではある)。
につき、
[加速器(小説[リング]表題と結びつく[リング]でもいい)遺構にてシュミレートされた世界(作中、ループ世界と呼称)]
[加速器遺構にてシュミレートされた仮想世界(作中、ループ世界と呼称)で猛威を振るう亡霊による時限性の絶対死]
[加速器遺構にてシュミレートされた仮想世界(作中、ループ世界と呼称)で亡霊の現われてくる地に開いた穴(井戸)]
[加速器遺構にてシュミレートされた仮想世界(作中、ループ世界と呼称)での亡霊の増殖プロセス]
との兼ね合いで何が述べたいのかは、そう、[増殖・拡大すれば人類に破滅を進呈することになるだろう加速器(リング)に由来するブラックホール生成]との兼ね合いで何が述べたいのかは ――先行するところで[黄金の林檎]について何を述べてきたのかお含みいただければ―― お分かりいただけるところか、とは思う。
ここで「奇怪なのは、」後に映画化されもしたリング・シリーズの続編たる『ループ』という小説の初版が世に出たとの、
[1998年]
という折柄は
[加速器とブラックホール生成の可能性が何ら結びつけられて「いなかった」時である]
とのことがあることである。
加速器とブラックホール生成が結びつけられるようになったのは、(本稿の前半部でその指し示しに注力しているように)、ウォルター・ワグナー申しようが巷間にて問題視されるようになった(だが、「当初」、加速器運営機関はブラックホール生成の可能性について完全否定していた)との「1999年」以降となり、対して、リング・シリーズにあって「そうきたか、」との落ちをつけた『ループ』が世に出た1998年 ――同1998年、ADDモデルという加速器によるブラックホール生成可能性肯定に「後に」つなげられることになった理論が世に出た年でもある―― という時節はその1999年に先立つこと1年前のこと、そう、物見高い向きも[加速器とブラックホール生成の関係性]といったことをおよそ着目できていないとの折であったとのことがある。
それがゆえに、
「[先覚性]が気がかりなところとなる」
と述べたいのである(:この馬鹿げた世界では[たかだかものその程度の予見性]のことを問題視する人間さえ存在しないわけだが(筆者のような人間がこうも書くとオンライン上に同文のことを[実にもって頭の具合のよろしくはない]との筆致、軽侮を招くが関の山であろうなといった筆致で目立って書き、かつ、といった筋目の類に由来する馬鹿げた言いようの伝ばかりが目に付くようになるとのこともありうると見るわけだが(そういうふざけたやりよう・ありようとの兼ね合いでは[前例]として思い当たるところが山とある)、取りあえず「現行は」その程度のことを問題視する人間さえ存在しない)、小説『ループ』の帰結、それが[貞子というシステムのバグが引き起こしたガン化プロセスが仮想世界を越えて現実世界への侵襲]ともなり、[人類の遠からずもの破滅]が作中にて示唆されているということもあわせて筆者などは「非常に不気味である」ととらえているところである)。
そして、リングとくれば、
[黄金の林檎]
との兼ね合いで直近引き合いに出したリヒャルト・ワグナーの戯曲『ニーベルングの指輪』のよく知られた英語版通称 The Ring(先述)を想起させるものであるとのこともある ――※[繋がらぬところを無理矢理に繋げている]との認識は元よりこの身、筆者にはない。 第一。ワグナーの Der
Ring des Nibelungen『ニーベルングの指輪』の通用化しての英文呼称は The Ringだが(英文Wikipedia[ Der
Ring des Nibelungen ]項目冒頭部にて現行、 It is often referred to as the Ring Cycle, Wagner's Ring, or simply the Ring.
と記載されているとおりである)、それと全く同じタイトルの The Ring『ザ・リング』が小説『リング』(1991年初出/その続編が年に1998世に出た加速器遺構による世界シュミレートを描く『ループ』)を映画化してのハリウッド映画化版の『リング』タイトルとなっているとのことが「ある」(2002年に皆既日食と紐付くかたちでハリウッド映画化版『「ザ」・リング』が世に出ている)。 第二。小説『リング』シリーズも戯曲『ニーベルングの指輪』も[加速器]との接点が重きをなす作品となっているとのこともが「ある」(前者については直近にて表記したとおりである(貞子なる存在の発生源が加速器の遺構にて構築されたグリッド・コンピューティング環境であったとされている)。また、後者については[黄金の林檎][アトラス][アトランティス]を介しての関係性について何度も何度も本稿にて解説してきたところである)。 につき、(飛躍に次ぐ飛躍のように感じるとの向きもあるかもしれぬが)、小説『リング』シリーズの映画化に関与してきた中田秀夫という映画監督がいる。有名所にも数えられる同映画監督がメガホンを取った作品として『MONSTERZ』という邦画作品が本稿本段を書き記している現時点から見て「ここ最近」、公開開始されているのだが(2014年5月公開/筆者が二年間続いた国内初かつ唯一のものであったLHC裁判第一審を終え、その控訴人として激昂させられることになったここつい最近のことである)、[興味深い内容であろう]と前宣伝文句から判じ、映画館に足を運んで視てみた同映画、ラストの一幕では『ニーベルングの指輪』(の中のドイツ語タイトルオペラ Die Walküre『ワルキューレ』)が演じられているとの[日本文化会館]([文化会館]とはそこに集う創価学会成員にはお馴染みの呼称であろう)で[マリオネットと化した人間を操る男]と[操られない男]の死闘が繰り広げられることになっているとの描写がなされていた。 そこからしてワグナーの[ニーベルングの指輪](本稿を公開しているサイトの一などで今よりかなり前から問題視してきた作品でもある)と[井戸から時限性の致死性かつ増殖性の亡霊が現れてくるリング・シリーズ]が[同じくもの映画監督]を通じて結びついていると見受けられるようになっている。その点、筆者が『この世界の現実の縮図か』と不快に思ったのは同映画『MONSTERZ』にて主人公(操られない男)と[人間をまるで触手かなにかのように操る男]の闘いの中で人間を操る男の方が『ニーベルングの指輪』が演じられての日本文化会館ホールでの死闘にて「ここにいる連中は何も分かっていない.思い出すことさえできない(だから殺されていくだけだ)」「どっちが勝つか.多数の俺と一人のお前と」などと駒人間らを価値無き命と軽侮しながら、かつ、実際に芥子粒のように扱って(文化会館に集まった)「彼ら」をただの戯れに自殺させたりしながら、「彼ら」を[マス;集団]として主人公にけしかけ、肉薄させしめ(集団と化し自主的思考能力を喪失したゾンビ人間らが主人公によってたかって取りつかんとするシーンは不気味さ・迫真性という意味で並みのゾンビ映画を陵駕すると筆者などは私的には見ている)、といった死闘が極まっての中、最期は[[創価学会系タレントとしてよく知られている女優]に足を引っ張られる主人公]と一緒にそちら[人間を操る男]が[螺旋階段]に真っ逆さまに落ちて行く描写がなされていたりもするシーンも(つい最近劇場で視てみた)当該の映画の中には含まれているとのことがある(残念ながらそういったところからして露骨なメタファーとして成立している節がある (そういうメタファー通りの状況が「現実に」ありそうなことにまつわって筆者がカルトの成員に対して名状しがたい怒りや嫌悪感を覚えるのは、である。【自分でものを考えられぬ、そして、終局的には殺されていくだけだろうとの状況】がそこにあっても絶対にそれを見ようとせぬし、社会的におなじくものありようを他に巧妙・確実に押しつけるための装置であろうと容易に推し量れるようになっている筋目・分際の団体に属する個々の者らの【人間としての醜さ】(低劣さでもいい)を捕捉しているとのことにある。無恥・無知を呈してのありようで「彼ら」宗教に根差した差別をこととする団体の者らが彼らの「外部」の敵対者(敵対者認定を彼らの方で「させられている」存在とした方が正確か)に対して「自分達こそ正しい.自分達こそ世の主役であり、敵対者と判じた(判じさせられたが正確だろうが)者らは組織的に徹底的に世の中から排除する」などと実にもって傲慢かつ不条理に動いていると透けて見える側面が「よくもある」とのことを、そう、筆者は知っており、といったありように名状しがたい怒りや嫌悪感を覚えるのだ ―確かにそうもした者達ならば彼らに機械じかけの神を与えて使嗾(しそう;使役)する者達からも映画よろしく「下らぬ芥子粒のような者達だ」と嘲笑われようかとは思う(筆者、この身は奇縁、圧力にさらされての来歴あって「彼らの」諸所の【コロニー】の動きなど「も」知るに至っているから経験に依拠してそうも述べるのだ)― ))。 が、といったことはここでは【行き過ぎの申しよう】ととらえてもらってもいい。ただ、この世界には「然りの如し」で多くのことに関連性が成立するようになってしまっていることは[闘う能力を有した人間](筆者のような人間「以外」にそういう向きがそうそうにいるのかとさえ現時、悲観的にならざるをえないと判じているが、とにかくも、仮にいたらば、のといった向き)には把握いただきたいとも考えている(「問題は、」そうした意志表示がかってのやりようが表出しているのが[属人的心証が極まってのあやまてる見解]で済むか、[確たる恣意性の賜物]なのか、そして、恣意の賜物ならば、その先には何が控えているのか、であるとしつつも、である))―― )
(補足としての話をしたためての部はここまでとしておく)
直上付記の部では国内サブカルチャー作品(小説『リング・シリーズ』)などを引き合いに行き過ぎもしていると思われかねない話をなしもしたが、とにかくも、である。
ii.「[パリスの審判]と[エデンの園]の誘惑の方は確かに複合的なる接合性を呈しているようだが、ただし、パリスの審判での林檎が[誘惑者の取得目標物]であったのに対して、エデンの園の誘惑にての禁断の果実(林檎とも見られることがある果実)は[誘惑の具]となっているものである。[目標]と[手段]との差異があるところで同一性を問題視するのもどうかととれるところである」
とのありうべき反論に対しては、
「本稿にて[際立っての要素]を持つ代表的古典として問題視しているミルトン『失楽園』ではサタンが林檎としての誘惑の果実(知恵の樹の実)で人間を堕落させたと描写されるわけだが、そのやりようを罰するとのかたちで神がサタンらをして[林檎への依存者]に仕立て上げたと描写されて「も」いることがある。すなわち、堕地獄を見たサタン(ルシファー)を長と戴く堕天使らは[林檎(知恵の樹の実)]なくして生きて行けぬ身体に神にされたなどと描写されているとのことがある(聖書には見られないとのそのようなアレンジがどうしてなされているのか、そう、[何故なのか]の問題は置き、とにかくもそういう描写がなされているとのことがある)。
林檎は誘惑の具であるのと同時に悪魔らの[神に強いられての(常態的なといった式での)渇望の対象]にも変じていると『失楽園』で描かれているわけであるが、それはパリスの審判にて([明けの明星]ルシファーよろしく金星と結びつく)アフロディテが黄金の林檎を是が非でも取得しようとしていたと描写されていること、また、(後述するところとして)北欧神話にて[黄金の林檎]が神々に不死を約束するためのなくてはならぬ常食とされていたことと話が接合するところである」
との方向性での再反論がなせるとここまでにて示した。
さて、対して、もうひとつ筆者物言いに対してそうした反論がなされてもおかしくはないとのことで(筆者より代弁するかたちでながら)挙げもしたこと、
i.「(蛇による不死の略取との側面が介在していても)[ギルガメシュ叙事詩]と[エデンからの追放の物語]はそれら全体が密接につながっているわけではない。であるから、両者の一部類似性を過度にピックアップして立論展開をなすのは良心的なやりようではない」
との申しようについてだが、直近まで述べてきたこととあわせもしてそちらもまた斥けられる、しかも、その斥けのための指し示しによって本稿本段にあって主軸として問題視していること、
[ギルガメシュ叙事詩およびミルトン『失楽園』が結合するようになっている(しかもその結合性がブラックホールにまつわる事物らとの兼ね合いで「も」際立っての多重性を呈しているが如くものとなっている)]
とのことまでもが指し示されるところとなっているとのことがある(それだけ聞く限りでは無論、[奇態]を越えて[意味不明なる話]とはなろうか、とも思うのだが)。
ここでのギルガメシュ叙事詩とエデンの追放(を描いた失楽園)を濃密に接合させることについての話で問題となるのは
[黄金の林檎](ヘラクレス11番目の功業にて登場し、また、トロイアの破滅の原因になった ―出典(Source)紹介の部39― との伝説の果実)
である。
またもやの黄金の林檎を介在させての関係性、その点について以降の段では(続けて表記の)a.からc.の流れで訴求をなすことにする。