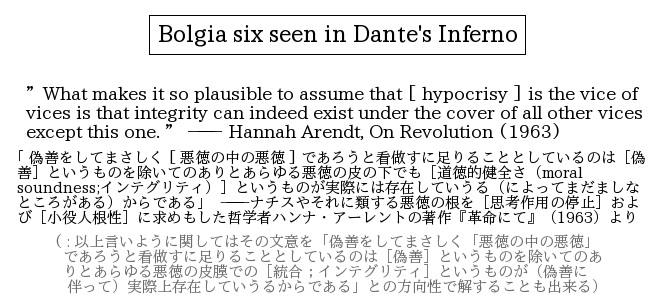[黄金の林檎]と[エデンの誘惑]の多重的関係性について[3]
本稿本セクションでは次の通りのことを問題視している。
ヘラクレス11番目の功業に登場する[黄金の林檎]については
「黄金の林檎は
「聖書『創世記』に見る[エデンの蛇による誘惑の物語]とも ――「トロイア崩壊に至るまでのエピソードを媒介項にする」とのかたちで―― 多重的に関わっている」
と「記号論的に」摘示可能なものとなっている」
とのことがある。
また、さらに一歩進んで、
「黄金の林檎が聖書『創世記』に見る[エデンの蛇による誘惑の物語]とも ――「トロイア崩壊に至るまでのエピソードを媒介項にする」とのかたちで―― 多重的に関わっていると「記号論的に」摘示可能なものとなっているとのことが
[ブラックホール生成問題]
と「あまりにもできすぎた」方向性にてつながるようになっている」
とのこと「も」がある。
これ以降は同じくものことら、
[[ヘラクレスの11番目の功業に登場する黄金の林檎]が[エデンの園の蛇の誘惑]に関わる]
[[ヘラクレスの11番目の功業に登場する黄金の林檎]が[エデンの園の蛇の誘惑]に関わるとのことからしてブラックホール生成問題と結びつくようになっているとのことが ――実にもって問題となる文献的記録らを通じて―― 指摘できるようになっている]
とのことらが ―いかほどまでに響きが奇態なるものであっても―
[個人の主観より生じ、また、そこに留まって然るべきと看做されよう印象論上の話]
などではまったくもってなく、「はきと客観的に指し示せるものとなっている」ことを証示すべくもの細かくもの指し示しをなしていく。
上にて本稿本セクションの主題として呈示したこととの絡みで直前頁までにて次のことらの段階的指し示しをなしていった。
a.[黄金の林檎にまつわる誘惑]および[エデンの園にての誘惑]の双方ともに[女という性を用いての誘惑]が主軸をなしているとのことがある(一方はヘレン、もう一方はイーヴという女という性を用いての誘惑がなされている⇒同じくものこと、トロイアありようにまつわる古典上の典拠は出典(Source)紹介の部39にて紹介している)。
b.[黄金の林檎にまつわる誘惑]および[エデンの園にての誘惑]の双方ともに[誘惑が破滅的事態をもたらした]との結末がつきまっているとのことがある(片方が[フォール・オブ・トロイア;トロイア陥落]、もう片方が[フォール・オブ・マン;人類の堕落・失楽園]との結末に通じている⇒同じくものこと、トロイアありようにまつわる伝承上の典拠は出典(Source)紹介の部39にて紹介している)。
c.[黄金の林檎にまつわる誘惑]および[エデンの園にての誘惑]の双方ともに誘惑にてその授受が争われたのは[林檎]および[林檎と歴史的に同一視されてきたもの]となっているとのことがある(聖書にては[エデンの禁断の果実]ことフォゥビドゥン・フルーツが[林檎]であるとの明示的表記がみとめられないわけであるが、それが歴史的ありようとして林檎と看做されてきたとのことがあり、本稿ではその点についても解説している ―出典(Source)紹介の部50を参照されたい― )。
d.[黄金の林檎の果樹園]は百頭竜ラドンに守られているとされる。そして、ギリシャ・ローマ時代における竜とは[巨大な蛇]のようなものであるとされる(出典(Source)紹介の部50の後に続けての部で典拠紹介のこと)。他面、[エデンの園の誘惑]は蛇によってなされたと伝わるものである。従って、[黄金の林檎]および[エデンの園の禁断の果実]の双方ともどもに[(蛇たる)爬虫類とのつながり]があいが見てとれるとのことになる。
e.[黄金の林檎にまつわる誘惑]および[エデンの園にての誘惑]の双方ともにあって[金星の体現化存在]が誘惑者となっているとのことがある(片方は金星の体現存在たる女神アフロディテを誘惑者としており、もう片方では金星(明けの明星)の体現存在たるルシファーことエデンの蛇と同一視されるサタンを誘惑者としている ―出典(Source)紹介の部48および出典(Source)紹介の部49― )。また、誘惑者が金星と結びつくだけではなく、黄金の林檎というのはそれが実る果樹園からして[金星]と親和性が高い存在となっているとのことがある。すなわち、黄金の林檎を果樹園で管掌するとされるヘスペリデスらが金星こと[宵の明星]と非常に近しい存在であるとのことがある(ヘスペリデスHesperidesという黄金の林檎の管掌者らは[金星=宵の明星]と同義のローマ名を持つHesperusを父親とするとも言われ、その構成単位ないし母親をHesperisとするとも言われる存在とのことになり、Hesperidesという[Hesper]との語句と結びつく黄金の林檎の管掌者らがいかに日没にて輝く金星と結びつくか推し量れもするとのことがある ―出典(Source)紹介の部49などを参照のこと― )。
f.[黄金の林檎の園]および[エデンの園]の双方は「互いに関係があるもの」として欧州人に「歴史的に」隠喩的・明示的な式で結びつけられてきたものらとなる。隠喩的な式とのことで言えば、ルネサンス期画家のルーカス・クラナッハ・ジ・エルダーの絵画に両者関係性を示唆するが如きものが存在しているとのことがある(その[具体例]を本稿の先の段、出典(Source)紹介の部51で挙げている)。他面、明示的な式で関係づける式とのことで言えば、近代知識人らの著作にあって[[神に不死を約束するネクター]と結びつく黄金の林檎の園]と[[不死と知恵の果実が実るエデンの園]とを結びつける表記がなされている(そちらも原文引用を出典(Source)紹介の部51でなしている)。


以上の指し示しをなし終えた段階で
[[ヘラクレスの11番目の功業に登場する黄金の林檎]が[エデンの園の蛇の誘惑]に関わるとのことからしてブラックホール生成問題と結びつくようになっているとのことが ――実にもって問題となる文献的記録らを通じて―― 指摘できるようになっている]
とのことを証示するための[布石]となるところである(「[ブラックホール生成問題を巡る「多重的」接合関係]を論ずるうえでの[布石]となるところである)と明示して論じてきたとの、
[ヘラクレス11番目の功業 ――(こちらヘラクレス第11功業に登場する[巨人アトラス]および[黄金の林檎]を巡る話がいかようにしてLHC実験と多重的に接合しているかは先に具体的典拠を挙げ連ねながら先立っての段にて詳述に詳述を重ねてきたこととなる)―― にあっての[黄金の林檎](トロイア崩壊の原因たるもの)が聖書『創世記』に見るエデンの蛇による誘惑の物語と接合している]
とのことについて多くを指し示したかたちとなる。
が、「まだ足りない」との認識にてこれ以降は同じくものことに通ずるところとして、
「さらにも、」
の話を ――話の方向性につき「多少」、というより、「かなり」の変化球を加えての格好にて―― 同様に[布石]となるところとしてなしていくこととする。
そうした変化球加えての以降の話にあっては、まずもって、
(「切り出しとしては唐突ながら結果的には取り上げているところの[多重的接合性]の問題を示す方向に収束していく」と申し添えたいとのところとして)
「コロンブスが[新大陸]として発見した[アメリカ]こそが[古のアトランティス]であると看做す風潮が大航海時代以降の欧州にあった」
「そちらをアトランティスと看做す風潮が欧州人にあったとのコロンブスが「発見」した[アメリカ]にあってはケツァルコアトル信仰というものがかつて存在しており、同ケツァルコアトル信仰が[エデンの蛇の物語]と接続するような要素を多重的に伴っていると示せるよう「にも」なっているとのことがある」
とのことらについての解説を講じることからはじめることとする ――事前に断っておくところとして、それら解説部からしてかなりの紙幅を割くことになる―― 。
まず、上にてのことらのうち、
「[アメリカ]こそが[古のアトランティス]であると看做す風潮が大航海時代以降の欧州にあった」
とのことについてだが、次の出典部紹介部を参照いただきたき次第である。

ここ出典(Source)紹介の部52にあっては、
「[アメリカ]こそが[古のアトランティス]であると看做す風潮が大航海時代以降の欧州にあった」
とのことの出典を挙げることとする。
その点、表記のことの指し示しにはそこからはじめる必要があると考えるためにそこから言及なすのだが、イングランドの著名な論客に
[フランシス・ベーコン]
という人物がいる。
同フランシス・ベーコンについては日本にあっても高等学校の[世界史]の科目を受験を使うことに選択した者がその名を
[近代的思想への道筋を付けた論客]
として暗記を強いられるような格好ともなっている歴史上の人物となる ――[知識通用度]の問題としてそうもなっている―― 。
にまつわっては和文ウィキペディアのフランシス・ベーコンにまつわる現行の記述を ――そも、フランシス・ベーコンの名など知らぬ存ぜぬとの向きが読み手になっていることを想定のうえで―― 引いておくこととする。
(直下、和文ウィキペディア[フランシス・ベーコン (哲学者)]項目にての現行の記載内容よりの一部引用をなすとして)

フランシス・ベーコン( Francis Bacon, Baron Verulam and Viscount St. Albans、1561年1月22日 - 1626年4月9日)は、イギリスの哲学者、神学者、法学者である。イングランド近世(ルネサンス期)の人物。「知識は力なり」( Ipsa scientia potestas est )の名言で有名。・・・(中略)・・・ヴォルテールは、フランシス・ベーコンついて、『ノヴム・オルガヌム』などの著作を念頭に、「経験哲学の祖」として賞賛している。

(引用部はここまでとする)
(続いて、直下、和文ウィキペディア[イドラ]項目にての現行の記載内容よりの一部引用をなすとして)

イギリス経験論哲学の祖として知られ、政治家でもあったフランシス・ベーコンは、「知識は力なり」のことばによって、自然の探求によって自然を克服し、人類に福祉をもたらすことを提案した。そして、その探求方法としては、法則から事実を予見するアリストテレス(『オルガノン』)的な演繹法に対し、個々の実験や観察の結果得られた知見を整理・総合することで法則性を見出す帰納法を提唱した。ベーコンによれば、一般論から個々の結論を引き出すアリストテレスの論理学はかえって飛躍をまねきやすいのであり、知識とはむしろ、つねに経験からスタートし、慎重で段階的な論理的過程をたどることによって得られるものであった。

(引用部はここまでとする)
さて、以上、前提知識ない向きを想定しての教科書的なフランシス・ベーコンにまつわる解説の引用をなしたところで述べるが、フランシス・ベーコンは
New Atlantis『ニュー・アトランティス』
という書籍をものしており、の中では、
「アメリカこそが伝説に見る大アトランティスである」
との言及がなされている(:英文・和文で『ニュー・アトランティス』の全内容を当然に検討している人間として申し述べておくが、同作『ニュー・アトランティス』というのは交易対象としての日本を目指していた欧州の船乗り達が(アメリカに同定されるグレート・アトランティスに対してそうも呼称される)[架空の島国ニュー・アトランティス]に漂着、そこでもって[サロモン(ソロモン)の家]という組織によって[文明の進歩のすばらしさ]を思い知らされるとの一種の寓意譚となっており、また、現実世界の英国にて[王立協会](人類の科学文明の進歩に多大なる役割を果たした科学者らの互助組織となり、アイザック・ニュートンが初期会長になっていたことでも知られる団体)の設立に影響を与えたとされる作品ともなっている ――その程度のことも物事を皮相でとらえるにすぎない世俗的教養のレベルに属する話ともなり(フランシス・ベーコンの名前を中世のロジャー・ベーコンという名前の際立っての修道士の名前と分けて暗記することを強いられる日本の受験生ら、および、彼らが長じてそうしたものとなるとの[「良き」社会の構成ユニット]の「過半」は死ぬまで把握することがないことかもしれないが、それでも世俗的教養のレベルに属する話ともなり)、例えば、英文Wikipediaにての[ New Atlantis ]項目にあっても常識的なところとして(掻い摘まんで引用なすところとして) New Atlantis is an incomplete utopian novel by Sir Francis Bacon, published
in 1627. In this work, Bacon portrayed a vision of the future of human
discovery and knowledge, expressing his aspirations and ideals for humankind.
[ . . . ] The plan and organisation of his ideal college, Salomon's House (or Solomon's
House), envisioned the modern research university in both applied and pure
sciences.[ . . . ] New Atlantis and other writings of Bacon inspired the formation of the
Royal Society.
(訳として)「ニュー・アトランティスは1627年に刊行されたフランシス・ベーコン卿の手になる未完のユートピア小説となる。この作品にてベーコンは彼の人類に対する切望・理想を吐露しながら人類の発見と知識の未来像を描いている。・・・(中略)・・・(ベーコンが自身の理想を体現すべくも呈示せんとした)彼の計画および理想の[サロモンの家(ソロモンの家)]の組織にまつわる部は近代以降の応用科学および純粋科学双方にあっての研究をなす大学に対する予見をなすものであった。・・・(中略)・・・ニュー・アトランティスおよびベーコンの他の著作らは王立協会の設立を促すことになった」(引用部はここまでとする) と解説されているところである―― )。

以上、基本的なることにつき解説したうえでここでは New Atlantis『ニュー・アトランティス』のオンライン上、 Project Gutenbergのサイトより全文入手できる原著版と岩波文庫版として流通見ている邦訳版より
[アメリカがアトランティスであると表記されていることに関わるパート]
よりの原文引用を(それが本稿にての指し示し事項に関わるとの認識があるゆえに)事細かになしておくこととする。
(直下、 Project Gutenbergのサイトより全文入手できるとの New Atlantisの中にての架空の島国 New Atlantisにあっての[ソロモンの家の役職者]に由来する申しようの部 ―― the Governor of the city, that one of the Fathers of Salomon's Houseに由来する申しようの部―― よりの原文引用をなすとして)

You shall understand (that which perhaps you will scarce think credible) that about three thousand years ago, or somewhat more, the navigation of the world, (especially for remote voyages,) was greater than at this day. Do not think with yourselves, that I know not how much it is increased with you, within these six-score years: I know it well: and yet I say greater then than now; whether it was, that the example of the ark, that saved the remnant of men from the universal deluge, gave men confidence to adventure upon the waters; or what it was; but such is the truth. The Phoenicians, and especially the Tyrians, had great fleets. So had the Carthaginians their colony, which is yet further west. Toward the east the shipping of Egypt and of Palestine was likewise great. China also, and the great Atlantis, (that you call America,) which have now but junks and canoes, abounded then in tall ships. This island, (as appeareth by faithful registers of those times,) had then fifteen hundred strong ships, of great content. Of all this, there is with you sparing memory, or none; but we have large knowledge thereof.
[ . . . ]
At the same time, and an age after, or more, the inhabitants of the great Atlantis did flourish. For though the narration and description, which is made by a great man with you; that the descendants of Neptune planted there; and of the magnificent temple, palace, city, and hill; and the manifold streams of goodly navigable rivers, (which as so many chains environed the same site and temple); and the several degrees of ascent, whereby men did climb up to the same, as if it had been a scala coeli, be all poetical and fabulous: yet so much is true, that the said country of Atlantis, as well that of Peru, then called Coya, as that of Mexico, then named Tyrambel, were mighty and proud kingdoms in arms, shipping and riches: so mighty, as at one time ( or at least within the space of ten years ) they both made two great expeditions; they of Tyrambel through the Atlantic to the Mediterrane Sea; and they of Coya through the South Sea upon this our island: and for the former of these, which was into Europe, the same author amongst you ( as it seemeth ) had some relation from the Egyptian priest whom he cited.
[ . . . ]
But the divine revenge overtook not long after those proud enterprises. For within less than the space of one hundred years, the great Atlantis was utterly lost and destroyed: not by a great earthquake, as your man saith; (for that whole tract is little subject to earthquakes;) but by a particular' deluge or inundation; those countries having, at this day, far greater rivers and far higher mountains to pour down waters, than any part of the old world. But it is true that the same inundation was not deep; not past forty foot, in most places, from the ground; so that although it destroyed man and beast generally, yet some few wild inhabitants of the wood escaped.
[ . . . ]
So as marvel you not at the thin population of America, nor at the rudeness and ignorance of the people; for you must account your inhabitants of America as a young people; younger a thousand years, at the least, than the rest of the world: for that there was so much time between the universal flood and their particular inundation. For the poor remnant of human seed, which remained in their mountains, peopled the country again slowly, by little and little; and being simple and savage people, (not like Noah and his sons, which was the chief family of the earth;) they were not able to leave letters, arts, and civility to their posterity; and having likewise in their mountainous habitations been used (in respect of the extreme cold of those regions) to clothe themselves with the skins of tigers, bears, and great hairy goats, that they have in those parts; when after they came down into the valley, and found the intolerable heats which are there, and knew no means of lighter apparel, they were forced to begin the custom of going naked, which continueth at this day.

(オンライン上より全文確認できるとの原著表記(の現代語訳版)よりの引用はここまでとする)
上のオンライン上より確認できるとの『ニュー・アトランティス』原著テキストに対しての訳文、広くも流通を見ている岩波文庫版(川西進訳)の該当部の訳文は ――原文引用するところとして―― 次のようになっている。
(直下、国内にて流通している岩波文庫版『ニュー・アトランティス』より掻い摘まんでの原文引用をなすとして)

(岩波文庫版『ニュー・アトランティス』p.26からp.27よりの引用をなす)
「ぜひともおわかりいただきたいのは(もしかするとあなた方には到底信じられないかも知れませんが)約三千年、あるいはそれ以上前には、世界の航海は(特に遠洋航海は)今日より盛んだったのです。あなた方のお国で、ここ百二十年ほどの前に、航海が大いに行われるになったことを私どもは知らないわけではありません。それは良く知っておりますが、それでもあの頃の方が今より盛んだったのです。世界大洪水から少数の人々を救った(ノアの)箱舟の例が、海に船出する自信を人類に与えたのかどうかわかりませんが、いずれにせよ事実はそうだったのです。フェニキア人、特にツロ(ティルス)の人たちは大船団を持っていました。カルタゴ人もそうで、彼らはツロよりもさらに西の方に入植した人々です。東方には、エジプト人とパレスチナの船が盛んに出ていました。中国も、大アトランティス(あなた方がアメリカと呼んでおられるところです)も今でこそジャンクとカヌーしかありませんが、当時は大きな帆船を持っていました。
・・・(中略)・・・
(岩波文庫版『ニュー・アトランティス』p.28よりの一部引用をなす)
その当時から一世紀かそれ以上にわたって、大アトランティスの住民は栄えていました。あなた方の中の異人の一人(プラトン)は、ネプチューンの子孫がそこに定住したと語り、壮大な神殿、宮殿、街並み、丘陵、(その街と神殿を鎖の輪のように幾重にも囲む)船の通れるほど大きな無数の河による入り組んだ水路、「天の梯子」(「創世記」二八章十二節「ヤコブの階段」参照)のように神殿に向かって登る幾段もの階段のことなどを詩的に、空想を交えて記述していますが、確かなことは、このアトランティスという国は、当時コヤと呼ばれるペルー、ティランベルと名付けられていたメキシコと同じように、軍備、船団、豊かな資産を誇る強大な国だったことです。これらの国々がいかに強大であったかは同時に(あるいは少なくとも十年以内に)二つの大遠征をしていることからもわかります。ティランベルは大西洋を横切って地中海へ、コヤは南海(太平洋)を横切って私どもの島へ来たのです。前者、つまりヨーロッパ遠征については、(たぶん)先に述べたあなた方のお国の筆者が、エジプトの神官から聞いた話として、書いておられます(『ティマイオス』二四)。
・・・(中略)・・・
(岩波文庫版『ニュー・アトランティス』p.29よりの一部引用をなす)
しかし、これらの傲慢な企てに対する神の復讐がほどなく彼らに下されました。百年も経たぬ内に、大アトランティスは完全に破壊され、消滅しました。例の方(プラトン)は大地震によると言っていますが(その地方一帯はめったに地震の起こるところではありません)、大洪水、大氾濫が原因です。これらの国々は、現在でも、旧世界のどこよりも大きな河と高い山があり、水を押し流すのです。しかしその洪水はあまり深くはなく、たいていの場所で四〇フィート以内の水深で、人にも動物にも広く被害を及ぼしましたが、森に住む僅かな野蛮な住人たちは助かりました。
・・・(中略)・・・
(岩波文庫版『ニュー・アトランティス』p.30よりの一部引用をなす)
ですからアメリカの人口の希薄さに驚くことはありません。彼らが粗暴で無知なのも当然です。アメリカの住民は若い、世界の他の地域の住民に比べて、少なくとも一千年は若いということを考慮しなければなりません。(ノアの)大洪水から彼らだけを襲った洪水までにそれだけの間があったのです。山間部の生き残った人々は、徐々に人口を増やし、全土に広がっていきましたが(全人類の中心となる一族であったノアと彼の息子たちとは違い)単純な野蛮な連中ですから、文字も、技芸も、礼節も、後世に伝えることはできませんでした。

(訳書よりの掻い摘まんでの引用部はここまでとする)
以上引用の部、『ニュー・アトランティス』に見る[Fictionとしての創作人類史](といっても教訓を語るためにそれと分かるように創作されての人類史)にまつわる部にあってベーコンは
[かつてアメリカ大陸が大アトランティスであった]
[アメリカ大陸としての大アトランティスは神罰によるところの洪水によって破滅を見た](これはアトランティスのことを伝えたプラトンの『ティマイオス』の表記が[大地震に次ぐアトランティスの沈没]とあいなっていることを元にしての創作であろうとの部である)
[洪水後のアメリカ大陸では文明の再建に至らず、旧大陸に比して未開の状況に文明水準が留め置かれることになった]
との[設定]を
[ニュー・アトランティス(ペルーから船出した欧州人が漂着した未知の島にて往古より外界と途絶されて存在していたとの島国)にての文明促進組織[ソロモンの家]の役職者の弁になるところ]
として持ち出しているのである。
上のようにベーコン著作『ニュー・アトランティス』では先進文明を有しているその他文明世界から隔絶されての架空のニュー・アトランティスの人間(サロモンの家の構成員)がアメリカをして
[大洪水で一端、破滅の憂き目を見た大アトランティス(グレート・アトランティス)]
であると呼称しているとの記述が見られるわけだが(そして、そのアメリカの住民が文明的に遅れた状況にあるのは洪水の影響冷めやらぬところであるからだとも表記されているわけだが)、といった認識はフランシス・ベーコン以後に作成された欧州人の手になる地図にもよく現われている。
下をご覧頂きたい。

上の地図は18世紀に活動し声望を博していたとされる地図製作者 Robert de Vaugondyによって作製されたとの世界地図となり、(拡大部をご覧いただければお分かりいただけようが)、アメリカをしてアトランティスとするとの欧州人の認識が反映されているものとなっている。
ここで、何故、以上取り上げたようなベーコン認識や地図制作者やりようが垣間見れるのか、すなわち、「アメリカこそがアトランティスである」との認識が垣間見れるかと述べれば、表層的には、今日にアトランティスありようを伝える古代ギリシャ古典、プラトン『ティマイオス』に見るアトランティス像が(直下、再引用するように)
[アジアとリビアを合算したものよりも大きいヘラクレスの柱(地中海と大西洋を分かつジブラルタル海峡)の先にある陸塊]
とのかたちで[アメリカ大陸のそれを想起させるもの]であったことが大なるところとしてある、そのように自然に解されるようになっている。
(直下、[アトランティスがアメリカ大陸と見なされるだけの古典上の記載が存する]とのことを強調すべくものプラトン全集12(岩波書店刊行)『ティマィオス』収録部p.22-p.23よりの(出典(Source)紹介の部36と同じくものことを引いての)「再度の」引用をなすとして)
あの大洋には――あなた方の話によると、あなた方のほうでは「ヘラクレスの柱」と呼んでいるらしいが――その入口(ジブラルタル海峡)の前方に、一つの島があったのだ。そして、この島はリビュアとアジアを合わせたよりもなお大きなものであったが、そこからその島の他の島々へと当時の航海者は渡ることができたのであり、またその島々から、あの正真正銘の大洋をめぐっている、対岸の大陸全土へと渡ることができたのである
(:以上の再引用部についてはオンライン上で容易に確認できる英文テキストとして Project Gutenbergのサイトよりダウンロードできるとの TIMAEUS by Plato( Benjamin Jowettとの19世紀にあってのプラトン翻訳家の訳になるバージョン)にての This power came forth out of the Atlantic Ocean, for in those days the
Atlantic was navigable; and there was an island situated in front of the
straits which are by you called the Pillars of Heracles; the island was
larger than Libya and Asia put together, and was the way to other islands, and from these you might pass to the
whole of the opposite continent which surrounded the true ocean;
とのテキストも先に引いていた)
(出典(Source)紹介の部52はここまでとする)
さて、直近までの段にて、以降指し示していくと申し述べていたところの
「コロンブスが[新大陸]として発見した[アメリカ]こそが[古のアトランティス]であると看做す風潮が大航海時代以降の欧州にあった」
「そちらをアトランティスと看做す風潮が欧州人にあったとのコロンブスが「発見」した[アメリカ]にあってはケツァルコアトル信仰というものがかつて存在しており、同ケツァルコアトル信仰が[エデンの蛇の物語]と接続するような要素を多重的に伴っていると示せるよう「にも」なっているとのことがある」
との二つのことらのうちの前者(「[アメリカ]こそが[古のアトランティス]であると看做す風潮が大航海時代以降の欧州にあった」)についての解説を遺漏無くもなしたつもりだが、次いで、
「そちらをアトランティスと看做す風潮が欧州人にあったとのコロンブスが「発見」した[アメリカ]にあってはケツァルコアトル信仰というものがかつて存在しており、同ケツァルコアトル信仰が[エデンの蛇の物語]と接続するような要素を多重的に伴っていると示せるよう「にも」なっている」
とのことについてこれより ――多少長くなるが、―― 解説を講じていくこととする。
それにつき、基本的なるところとしてアステカ文明というものがどういうもので、そこにて隆盛を見ていたケツァルコアトル崇拝というものがいかようなるものであったかについて「教科書的な」言われようの紹介をなすことからはじめる。

ここ出典(Source)紹介の部53にあっては極々基本的な教科書的な知識の問題、その程度のものとの認識にて「まずもって」和文ウィキペディア[アステカ]項目より(手前が記述に間違いないだろうと見ているところより)抜粋なすことで同文明の概要を紹介することからはじめる。
(直下、高等学校学童レベルの話としてそこよりの引用で十分と考えたところとして和文ウィキペディア[アステカ]項目にての現行記載内容よりの掻い摘まんでの引用をなすとして)

アステカ(Azteca、古典ナワトル語:Aztēcah)とは1428年頃から1521年まで北米のメキシコ中央部に栄えたメソアメリカ文明の国家。自らをメシーカ(古典ナワトル語:mēxihcah)と称した。言語は古典ナワトル語(ナワトル語)。
[建国] 伝説によればアステカ人はアストランの地を出発し、狩猟などを行いながらメキシコ中央高原をさまよっていた。やがてテスココ、アスカポツァルコ、クルワカン、シャルトカン、オトンパンなどの都市国家が存在するメキシコ盆地に辿りつき、テスココ湖湖畔に定住した。1325(または1345)年、石の上に生えたサボテンに鷲がとまっていることを見たメシカ族は、これを町を建設するべき場所を示すものとしてテスココ湖の小島に都市・テノチティトランを築いた。その後、一部が分裂して近くの島に姉妹都市・トラテロルコを建設したとされる。
・・・(中略)・・・
[繁栄] 1440年、イツコアトルの後を継いでモクテスマ1世が即位する。モクテスマ1世は遠征を頻繁に行い、メキシコ湾岸の熱帯地方を占領・従属させて勢力を拡げた(花戦争)。征服した土地に対して貢ぎ物を要求したが統治はせず、自治を許していた。被征服地は度々反乱を起こしたが、武力で鎮圧された。
・・・(中略)・・・
[スペインのアステカ帝国征服] アステカにはテスカトリポカ神に追われた白い肌を持つケツァルコアトル神が『一の葦』の年(西暦1519年にあたる)に戻ってくる、という伝説が存在した。帰還したケツァルコアトルが古い世界を破壊して新しい世界を建設すると信じられていた。アステカ人が漠然と将来に不安を感じ始めていたころ、テノチティトランの上空に突然大きな火玉が現れ神殿の一部が焼け落ちてしまった。その後も次々と不吉な出来事が起こった。この伝説により、『一の葦』の年の2年前(1517年)から東沿岸に現れるようになったスペイン人は帰還したケツァルコアトル一行ではないかと受けとられ、アステカのスペイン人への対応を迷わせることになった。
・・・(中略)・・・
[滅亡] メソアメリカ付近に現れたスペイン人は、繁栄する先住民文化をキューバ総督ディエゴ・ベラスケスに報告した。1519年2月、ベラスケス総督の配下であったコンキスタドールのエルナン・コルテスは無断で16頭の馬と大砲や小銃で武装した500人の部下を率いてユカタン半島沿岸に向け出帆した。
・・・(中略)・・・
1519年11月18日、コルテス軍は首都テノチティトランへ到着し、モクテスマ2世は抵抗せずに歓待した。コルテス達はモクテスマ2世の父の宮殿に入り6日間を過ごしたが、ベラクルスのスペイン人がメシカ人によって殺害される事件が発生すると、クーデターを起こしてモクテスマ2世を支配下においた。
・・・(中略)・・・
その後スペインは金銀財宝を略奪し徹底的にテノチティトランを破壊しつくして、遺構の上に植民地ヌエバ・エスパーニャの首都(メキシコシティ)を建設した。多くの人々が旧大陸から伝わった疫病に感染して、そのため地域の人口が激減した(但し、当時の検視記録や医療記録からみて、もともと現地にあった出血熱のような疫病であるとも言われている)。
・・・(中略)・・・
その犠牲者は征服前の人口はおよそ1100万人であったと推測されるが、1600年の人口調査では、先住民の人口は100万程度になっていた。スペイン人は暴虐の限りを尽くしたうえに、疫病により免疫のない先住民はあっという間に激減した。
・・・(中略)・・・
アステカ社会を語る上で特筆すべきことは人身御供の神事である。人身御供は世界各地で普遍的に存在した儀式であるが、アステカのそれは他と比べて特異であった。メソアメリカでは太陽は消滅するという終末信仰が普及していて、人間の新鮮な心臓を神に奉げることで太陽の消滅を先延ばしすることが可能になると信じられていた。そのため人々は日常的に人身御供を行い生贄になった者の心臓を神に捧げた。また人々は神々に雨乞いや豊穣を祈願する際にも、人身御供の神事を行った。アステカは多くの生贄を必要としたので、生贄を確保するために戦争することもあった。ウィツィロポチトリに捧げられた生贄は、祭壇に据えられた石のテーブルの上に仰向けにされ、神官達が四肢を抑えて黒曜石のナイフで生きたまま胸部を切り裂き、手づかみで動いている心臓を摘出した。シペ・トテックに捧げられた生贄は、神官達が生きたまま生贄から生皮を剥ぎ取り、数週間纏って踊り狂った。人身御供の神事は目的に応じて様々な形態があり、生贄を火中に放り込む事もあった。

(引用部はここまでとする)
(出典(Source)紹介の部53はここまでとする)
以上、基本的なる解説のされようを引いたように現メキシコ界隈に拠って栄えていた(そしてスペインの侵出によって滅ぼされた)とのアステカで隆盛を見ていたケツァルコアトル信仰がいかなものかだが、(この手のことは衆目につきやすきウィキペディアなどの希釈化されての記述でさえ多くが知れるようになっているのであるも)、については、先アメリカ史(コロンブス到来前、プレ・コロンビアン・イラと海外では呼称される時代)の研究を一意専心とのかたちでなしてきたとの欧米の学者らにどのような定義付けがなされていたかを引くことまでなしたほうがよいか、と判断、そうしたソースよりの引用を以降なしていくこととする。

ここ出典(Source)紹介の部53(2)にあってはケツァルコアトル神が一体全体、どのような神として信仰されていたのか、概説紹介をなしているとの著作よりの引用をなしておく。
(直下、 Project Gutenbergのサイトにてダウンロードできるとの AMERICAN HERO-MYTHS. A STUDY IN THE NATIVE RELIGIONS OF THE WESTERN CONTINENT(1882) ――19世紀にて声望高かった Daniel Garrison Brintonダニエル・ガリソン・ブリントンという米国人考古学者の手になるアメリカ史分析書となり、直訳すれば、『アメリカの英雄神話:西方の大陸、その土着宗教の研究』とのタイトルの書籍―― にての The Return of Quetzalcoatl CHAPTER III. THE HERO-GOD OF THE AZTEC TRIBES. §1. The Two Antagonists.のパートよりの原文引用をなすとして)

The culture hero of the Aztecs was Quetzalcoatl, and the leading drama, the central myth, in all the extensive and intricate theology of the Nahuatl speaking tribes was his long contest with Tezcatlipoca, "a contest," observes an eminent Mexican antiquary, "which came to be the main element in the Nahuatl religion and the cause of its modifications, and which materially influenced the destinies of that race from its earliest epochs to the time of its destruction."
[ . . . ]
Like all the heroes of light, Quetzalcoatl is identified with the East. He is born there, and arrives from there, and hence Las Casas and others speak of him as from Yucatan, or as landing on the shores of the Mexican Gulf from some unknown land. His day of birth was that called Ce Acatl, One Reed, and by this name he is often known. But this sign is that of the East in Aztec symbolism.[2]
[ . . . ]
His name is symbolic, and is capable of several equally fair renderings. The first part of it, quetzalli, means literally a large, handsome green feather, such as were very highly prized by the natives. Hence it came to mean, in an adjective sense, precious, beautiful, beloved, admirable. The bird from which these feathers were obtained was the quetzal-tototl ( tototl, bird ) and is called by ornithologists Trogon splendens.
The latter part of the name, coatl, has in Aztec three entirely different meanings. It means a guest, also twins, and lastly, as a syncopated form of cohuatl, a serpent. Metaphorically, cohuatl meant something mysterious, and hence a supernatural being, a god. Thus Montezuma, when he built a temple in the city of Mexico dedicated to the whole body of divinities, a regular Pantheon, named it Coatecalli, the House of the Serpent.
(訳として)
「アステカにあっての文化的英雄はケツァルコアトルとなっており、ナワトル語を母語とする(同アステカ文明担い手たる)氏族全てにあっての広範囲に渡り、かつ、入り組んだ神話大系にあっての主要なる物語、中心に位置するとの神話は
[ケツァルコアトルとテストポリテカとの長きに渡る対立]
ともなっており、その対立は、衆に優れてのメキシコ古物蒐集家が述べるところ、
「ナワ族(ナワトルを母語とする民族)の宗教にての主要素、そして、その修正の因ともなり、その最も初期の物語から破壊の折に至るまでの民族の運命に影響を与えてのものとなっている」
とのことである。
・・・(中略)・・・
陽の側面を体現しての諸々の英雄らに認められるように、ケツァルコアトルは東との方向と紐付けられている存在となる。彼はそこにて生まれ、そこからやって来たとされ、同ケツァルコアトルにつきラス・カサス(訳注:スペインのインディオに対する虐殺にまつわる記録を遺したことでも有名なスペイン人修道士たる史家[バルトロメ・デ・ラス・カサス]のこと)や他の人間は[ユカタン半島あるいは未知なる土地からメキシコ湾海岸へやってきた存在]と言及している。彼の降誕の年はセーアカトル( Ce Acatl )、一の葦の年となっており、その絡みで彼ケツァルコアトルはしばしば知られるとのことになっている(訳注:19世紀後半に執筆されたここにての引用元書籍 AMERICAN HERO-MYTHS. A STUDY IN THE NATIVE RELIGIONS OF THE WESTERN CONTINENTにあってのこの部では[[ケツァルコアトルの帰還の年]とされる[一の葦の年]がスペイン人のエルナン・コルテスの到来期間と期を一にしていたため、現地民がスペイン人侵略者をケツァルコアトルと誤信された]とのことが言及されているのだと解される)。しかし、この[一の葦の年]の象徴はアステカシンボリズム体系にあっての東方のシンボルでもある。
・・・(中略)・・・
彼ケツァルコアトルの名前は象徴的なものであり、等しくも翻訳できるようなものとなっている。Quetzalcoatlにあってのquetzalliの部は地元民にとても珍重されているとの[大きく見事な緑色の羽毛]を意味する。そのうえでそちらquetzalliは形容詞的意味合いにて[高価な][美しい][親愛なる][賞嘆に値する]との意を有するに至っていた。それら羽毛の産出元としての鳥はquetzal-tototlとの鳥となり、鳥類学者によってトロゴン・スプレンデス、美しきキヌバエドリと呼ばれている鳥となる。Quetzalcoatlという語の後ろの部コアトルcoatlはアステカ人にとり、三つの意味を有しており、[客人]そして[双子ら]、最後に、cohuatlとの語と同義扱いされながらの[蛇]の意である。比喩的な文脈でとらえれば、(蛇を意味する)cohuatlとの語は神秘的な何物か、そして、霊的な存在、神との意味の語となっている。このようなところでモンテスマ(訳注:アステカ帝国の統治者)はメキシコ・シティが現在存在する場にて神々全神格に捧げる正規の万神殿(パンテオン)としてCoatecalli、[蛇の家]と名付けられた神殿を建立しもしていた」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
(出典(Source)紹介の部53(2)はここまでとする)
直上の部にて19世紀のその方面の権威 ――19世紀にて声望高かった Daniel Garrison Brinton(ダニエル・ガリスン・ブリントン)という米国人考古学者―― が自著の中にて述べていることを(プロジェクト・グーテンベルクのサイトより誰でもオンラインで確認できるところを引きながら)紹介したわけだが、そこにてケツァルコアトルは
[文化的英雄( the culture hero of the Aztecs )にして民族のありように最初から最後まで影響を与えた存在にして、[羽毛の生えた(quetzalli)蛇(cohuatlないしcohuatl)]との語に分解できる名前を有しもしている存在]
として言及されている。
そうもしたケツァルコアトルが
[金星の体現存在]
[文明の授け手]
として崇拝されていた存在となっていること、続いての典拠紹介部にて紹介したい。
| 出典(Source)紹介の部53(3) |

本段、出典(Source)紹介の部53(3)にあってはケツァルコアトルという神が[金星の体現存在][文明の授け手]としての特性を帯びていたことの出典を挙げることとする。
まずもって基本的なところから取り上げるとして、オンライン上にて即時即座に確認できるところの英文ウィキペディアには以下のような表記がなされている。
(直下、英文Wikipedia[Quetzalcoatl]項目の冒頭部よりしばらく下っての段にての現行記載よりの引用をなすとして)

Among the Aztecs, whose beliefs are the best-documented in the historical sources, Quetzalcoatl was related to gods of the wind, of Venus, of the dawn, of merchants and of arts, crafts and knowledge.
[ . . . ]
To the Aztecs, Quetzalcoatl was, as his name indicates, a feathered serpent, a flying reptile (much like a dragon), who was a boundary-maker (and transgressor) between earth and sky. He was a creator deity having contributed essentially to the creation of Mankind. He also had anthropomorphic forms, for example in his aspects as Ehecatl the wind god. Among the Aztecs, the name Quetzalcoatl was also a priestly title, as the two most important priests of the Aztec Templo Mayor were called "Quetzalcoatl Tlamacazqui". In the Aztec ritual calendar, different deities were associated with the cycle-of-year names: Quetzalcoatl was tied to the year Ce Acatl ( One Reed ), which correlates to the year 1519.
(訳として)
「歴史的資料(訳注:侵略者スペインサイドの資料)として極めてよく文書化されている信仰を有していたアステカの民らの間にてケツァルコアトルは風・[金星]・夜明け・商業・芸術・技能・知識の神々と関連付けさせられていた。・・・(中略)・・・アステカの民らにとってケツァルコアトルの名は[大地と空の境界線を定めた存在(そしてその境界の侵犯者)としてのドラゴン]と評するほうがより適切であろうといった[飛行する爬虫類]としての[羽毛ある蛇]のことを指し示すとのものとなる。同ケツァルコアトルは人間の創造に根本から関わっているとの創造神とみなされてもいる。また、ケツァルコアトルは風の神Ehecatlとしての側面にて人間の形態を取ることもある。アステカ人の間にてケツァルコアトルの名は神職の称号名となり、アステカの神殿にて最も重要な二つの神職位階は Quetzalcoatl Tlamacazquiと呼ばれるものであった。アステカの儀式上の暦では年単位の周期が異なる神々の名前と対応付けられており、ケツァルコアトルは[一の葦の年]と対応付けさせられており、それは1519年(訳注:スペインよりの征服者エルナン・コルテスがアステカ皇帝モンテズマと会見した年)と対応している」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
上では
[アステカの民らの間にてケツァルコアトルは風・[金星]・夜明け・商業・芸術・技能・知識の神々と関連付けさせられている]
とケツァルコアトルが金星の体現存在であることが示されているわけだが、同Quetzalcoatlが
[金星の体現存在]
とされていることにつきもう一押しの出典紹介をなしておく。
この手の出典候補としてはオンライン上より堅いところの出典がいくらでも見つかるようになっているのだが、ここではなかんずく手堅いところとして
The Archaeology of Measurement: Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies, Cambridge University Press, 2010(2010年、ケンブリッジ出版会刊行の『単位の考古学:古代社会にての天と地と時間に関する理解』とでも訳せよう書)
の記述を引いておくこととする。
(直下、 The Archaeology of Measurement: Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societiesにてのp.160の記述を引くとして)

The center of the pyramid divides this line at the Sacred Precinct into 416- and 584- molicpitl segments. The latter is the principal Venus cycle count. This is appropriate because the god Quetakoatl was associated with Venus as morning and evening star.
(大要訳として)
「(ケツァルコアトルの)ピラミッドの中央部はこの聖なる区域を(特定の規則に基づいての)二区画に分割する。後者は金星のサイクル計算と一致しているとのものとなる。これはケツァルコアトルが[明けの明星](モーニング・スター)にして[宵の明星](イブニング・スター)たる金星と関連づけられているとのことによる」

(引用部はここまでとする ――尚、表記の原著英文テキストは抜粋の文言でもってグーグル検索エンジンを走らせることで文献的事実であることを、(少なくとも現行にては)、確認可能となっている―― )
上にてケツァルコアトルが
[金星の体現存在]
として崇拝されていた存在となっていること、典拠紹介なしたわけだが、次いで、同神が文明の授け手であるとされることについても端的な引用をなしておきたい。
(直下、先程の段にてもそこよりの文言を引いたところの著作、 Project Gutenbergのサイトにてダウンロードできるとの AMERICAN HERO-MYTHS. A STUDY IN THE NATIVE RELIGIONS OF THE WESTERN CONTINENTにあっての The Return of Quetzalcoatl CHAPTER III. THE HERO-GOD OF THE AZTEC TRIBES. の部にての §3. Quetzalcoatl, the Hero of Tula.よりの引用をなすとして)

But it was not Quetzalcoatl the god, the mysterious creator of the visible world, on whom the thoughts of the Aztec race delighted to dwell, but on Quetzalcoatl, high priest in the glorious city of Tollan (Tula), the teacher of the arts, the wise lawgiver, the virtuous prince, the master builder and the merciful judge.
(訳として)
「ケツァルコアトルはアステカ民族が生きるに喜びを感じていた可視世界、その神秘的なる創造者との位置付けにある神ではないが、同ケツァルコアトルは栄華を誇ってのトゥーラ(訳注:アステカ勃興前にメキシコ界隈で栄えたトルテカ文明の都市群)よりの高位の祭司、技芸の教授者、賢明なる法制定者、美徳をもっての王子、建築家、慈悲深い審判者との存在であった」

(訳を振っての引用部はここまでとしておく ―※― )
(※尚、同じくもの点につき、衆目につきやすきところの英文Wikipedia[Quetzalcoatl]項目には historian David Carrasco has argued that the preeminent function of the
feathered serpent deity throughout Mesoamerican history was as the patron
deity of the Urban center, a god of culture and civilization.
「歴史家の David Carrascoはメソアメリカ史全体にわたっての羽毛ある蛇の役割が都市中枢にての庇護者としての神、文化文明の神としてのものであったことを論じている」と記載されているとのことがある)
(出典(Source)紹介の部53(3)はここまでとする)
これにてケツァルコアトルが
[金星の体現存在]
[文明の授け手]
として崇拝されていた存在となっていたことの指し示しを終える。