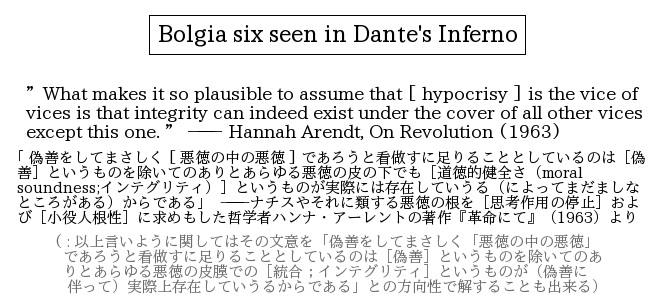ダンテ『地獄篇』とミルトン『失楽園』に見る(「今日的観点で見た場合の」)ブラックホール近似物に関して何が問題になるのかについて ――『ギルガメシュ叙事詩』を引き合いにして純・記号論的に述べられもすること[7]
直前頁末尾にあっては以下のこと、申し述べていた。
a.からc.、すなわち、

[(既にそちらにまつわる神話伝承の多重的連結関係は本稿で論じているところとなるのであるも「さらにもって」の話として)黄金の林檎にまつわる話は多くの神話・伝承を「不可解に」結節させるものである]

[上のa.に関わるところとして[ギルガメシュ伝承にあっての洪水伝承および蛇の不死の略奪に関わるパート](考古学者らに第11番目の石版と振られている『ギルガメシュ叙事詩』の特定パート)に関して「も」[黄金の林檎の取得が目標となっているとのヘラクレス第11功業]との顕著な純・記号論的連続性が認められることが現実に摘示可能となっている]

[上のa.及びb.(なかんずくb.)の[黄金の林檎]に関しての話は[エデンでの誘惑]とも密接に連結するものとなっている(につき、黄金の林檎とエデンの果実の関係性については本稿にてのより先立っての段で細かくも論じてきたことともなっている)。
既に指し示してきたところの[黄金の林檎とエデンの禁断の果実の関係性]が見てとれる中で(上のb.にて新たに呈示なしてのように)ギルガメシュ伝承までもが黄金の林檎にまつわる伝承と接合するとのことはミルトン『失楽園』の主題そのもの(エデンからの追放)が
[洪水伝承]
[蛇による不死の略取]
との双方の要素を帯びているギルガメシュ叙事詩特定パート(考古学者らに第11番目の石版と振られているパート)と ――かねてより摘示なしてきた[黄金の林檎]と[エデンの果実]の関係「も」あり―― 多重的に接合することに等しい。
そこより、
[[蛇による不死の略取の物語]とも言い換えられるミルトン『失楽園』 ―黄金の林檎と関わるエデンの果実を用いての誘惑のプロセスが描かれる物語― にあっての(黒海にて周囲に災厄を引き起こし海峡が構築されたとの)[洪水伝承]とつながり「うる」との(従前論じてきた)側面]
が
[つながり「うる」]
で済まされないようなものとの観点が出てくる。
また、
[[黄金の林檎]の在処を把握すると神話が語る巨人アトラス]
[[黄金の林檎]の園の同等物とも考えられてきた[洪水]で滅した伝説のアトランティス]
[[黄金の林檎]が原因ではじまった戦争にて住民皆殺しに遭った後、[洪水]で消滅したとの伝承が存するトロイア]
と結びつくとの側面を「どういうわけなのか」複合的に帯びているとの今日のLHC実験とミルトン『失楽園』との関係性もが同じくものことより「よりもって重層的なるかたちで」問題になるとのこともある(:ミルトン『失楽園』にあっての[トロイア][黄金の林檎を巡ってのパリスの審判と多重的類似要素を帯びてのエデンの誘惑][ブラックホール類似要素]とひとところにて接合するありようからLHC実験との接合性は指摘できるようになっている ――ミルトン『失楽園』に関しては[アトラス][アトランティス][トロイア崩壊をもたらした木製の馬の計略の考案者らを飲み込んだ渦潮の怪物カリブディス]らをすべて[ブラックホール生成]に通ずるところの命名規則として用いているLHC実験との接合性を指摘できるようになっている―― とのそのことが問題になる)]
とのことらにあっての、

[上のa.に関わるところとして[ギルガメシュ伝承にあっての洪水伝承および蛇の不死の略奪に関わるパート](考古学者らに第11番目の石版と振られている『ギルガメシュ叙事詩』の特定パート)に関して「も」[黄金の林檎の取得が目標となっているとのヘラクレス第11功業]との顕著な純・記号論的連続性が認められることが現実に摘示可能となっている]
の部の指し示しに「これより」歩を進める。
以上振り返ったうえでここ本頁では(振り返り部にあっての)b.のことの典拠紹介に入ることとする。
それにつき、続けての出典紹介部らにあっては
「重要なことであると見ているので典拠紹介に力を入れる」
と申し述べ、順々に
[ギルガメシュとヘラクレスの間には[[ビジュアル面]含めての存在としての特性]にあって共通性が見てとれるようになっている]
[伝承に見る、ギルガメシュ・ヘラクレスの両存在の「特定の」冒険とその冒険にての取得目標物には際立っての共通性が見てとれるようになっている]
とのことらについての典拠紹介をなしていくことととする。
それでは、まずもってそこより始めるとして、ここよりは
[ギルガメシュとヘラクレスの間には[[ビジュアル面]含めての存在としての特性]にあって共通性がある]
とのことについての解説をなすこととする。

上掲図にあっての左側にて挙げているのは Project Gutenbergのサイトにて全文公開されている CHALDEA FROM THE EARLIEST TIMES TO THE RISE OF ASSYRIA(1893年刊)にて掲載(p.306及びp.307掲載)の初期[Izdubar]と呼ばれていたギルガメシュの似姿を描いた図となる。
対して、右側にて挙げているのはルネサンス期イタリアにて画家アントニオ・デル・ポッライオーロ Antonio del Pollaioloによって15世紀に描かれた絵画、そこに見るヘラクレス像となる。
以上、左右に見てとれるギルガメシュとヘラクレスの両雄の間の際立っての類似性につき以降、順々に解説していく。
すぐに典拠紹介なすところとして以下のことが[ギルガメシュとヘラクレスの類似性]として指し示せるようになってもいる。
ギルガメシュは
[獅子を難なくいなす怪力]
の存在として偶像化され(図を挙げてそのことを示しておく)、今日にその似姿を留めている存在である。加えてギルガメシュはその叙事詩の中で
[ライオンの皮を被っている者]
と形容され、また、その獅子の皮かぶりにつき自己言及している存在ともなる(直下、出典(Source)紹介の部62を参照のこと)。
対して、ヘラクレスは
[ネメアの獅子という存在をその第十二功業の冒頭の第一功業で斃(たお)した存在]
として知られており、そうして誅したとのそのネメアの獅子を毛皮を防具とするに至ったとの存在、すなわち、
[獅子の皮かぶりをなしている存在]
とのかたちでよく偶像化されているとの存在ともなっている(直下、出典(Source)紹介の部62を参照のこと)。
まとめれば、ギルガメシュもヘラクレスも「獅子をいなし」「獅子の皮を被っている」存在となっている。

ここ出典(Source)紹介の部63にあっては
[ギルガメシュとヘラクレスの[獅子をいなす英雄][獅子の皮かぶりの英雄]との特質]
にまつわる典拠を挙げることとする。

上掲図[左側]は Project Gutenbergのサイトより全文ダウンロードできるとの19世紀末(1893年)刊行の CHALDEA FROM THE EARLIEST TIMES TO THE RISE OF ASSYRIA(訳せば、『その草創期からアッシリアの台頭までのカルデア』となろうとの著作)にて掲載されている初期 Izdubarと呼ばれていたギルガメシュ似姿を彫った遺物の模写となる(同図については英文Wikipedia[Gilgamesh]項目にあっては The Chaldean Account of Genesis(1876)『カルデア人の創世記に対する説明』という他の Project Gutenberg公開著作にて掲載されているものとして挙げられている図となりもする)。
上掲図[右側]はその確度・真偽の問題はさておきも紀元前6世紀(前520年から前500年)の作として英文Wikipedia[ Nemean lion ]項目に掲載されている[ネメアの獅子と闘うヘラクレス像を描いたオイノコエ(水差し)に見る画]となる。
(→上の如き偶像化様式に見てとれるところとして、ギルガメシュおよびヘラクレスが[獅子を素手にていなす英雄]として描写されていること、理解いただけたか、とは思う)
以下にあってはギルガメシュが([獅子をいなす存在]として偶像化されての似姿が発掘されている存在であるだけではなく)[獅子の皮かぶりの英雄]と字面にて叙述されていることの典拠を挙げておくこととする。
岩波書店より出されている邦訳版『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店/訳者はアッシリア学者の月本昭男立教大教授)の[第10の書版]と振られた出土碑文の内容が訳され掲載されているとの箇所、そこにて見受けられる、
[シドゥリという神(ギルガメシュに死すべき者としての理想的生活につき諭したとのことで知られる女神)とギルガメシュのやりとり]
の段にてギルガメシュは次のように記載されているとの存在ともなる。
(直下、岩波書店より出されている邦訳版『ギルガメシュ叙事詩』p.138よりの原文引用をなすとして)

43あなたの顔は[遠い道のりを行く者のようです。]
44あなたの顔は[暑さと寒さで]焼けついている。
45あなたは[ライオンの毛皮を纏って、]荒野をさまよう。
46[ギルガメシュは酌]婦[シドゥリに語った。]
47「[なぜ、わが頬がやせこけ、顔が落ち込まずにあり得よう。」
48[わが心が憔悴し、わが姿が消沈せずにあり得よう。]
49[悲嘆がわが胸に押し寄せずにあり得ようか。]
50[わが顔が遠い道のりを行く者のようでなくあり得ようか。]
51[わが顔が暑さと寒さで焼けつかずにあり得ようか。]
52[わたしがライオンの毛皮を纏って、荒野をさまよわずにいられようか。]

(引用部はここまでとする)
上の碑文解読表記に見るようにギルガメシュは[獅子の皮をまとった英雄]としての側面を持つ存在である。
その点、上にて引用したような書版上の記述がなされている背景には
[ギルガメシュが親友エンキドゥの死に際会して「獅子の皮を被って」の姿で野山を遍歴するに至った]
との背景がある(と伝わる)。
については THE EPIC OF GILGAMESH『ギルガメシュ叙事詩』英訳版としてオンライン上にてPDF文書形式で流通している版 ――文書タイトルの THE EPIC OF GILGAMESHと同組織名をあわせて検索すれば、文書特定できようとの[ Assyrian International News Agency ]ことアッシリア文化の促進団体としての組織体より刊行されている版――、その ISHTAR AND GILGAMESH, AND THE DEATH OF ENKIDU(イシュタルとギルガメシュ、そして、エンキドゥの死)と付された部、p.13にての表記を原文抜粋との形態で引いておくこととする。
(直下、[ Assyrian International News Agency ]ことアッシリア文化の促進団体としての組織体より刊行されている版にての THE EPIC OF GILGAMESH『ギルガメシュ叙事詩』英訳版よりの引用をなすところとして)

When Shamash heard the words of Enkidu he called to him from heaven: ‘Enkidu, why are you cursing the woman, the mistress who taught you to eat bread fit for gods and drink wine of kings? She who put upon you a ‘magnificent garment, did she not give you glorious Gilgamesh for your companion, and has not Gilgamesh, your own brother, made you rest on a 'royal bed and recline on a couch at his left hand? He has made the princes of the earth kiss your feet, and now all the people of Uruk lament and wail over you. When you are dead he will let his hair grow long for your sake, he will wear a lion's pelt and wander through the desert.'
(補ってもの訳をなすとして)
「シャマシュ(メソポタミアの太陽神)が死せるエンキドゥの声を聞いたとき、彼シャマシュは天よりエンキドゥに語りかけた。[エンキドゥよ。なぜ、汝はそうも女を、汝に神々に相応しきパンを食すこと、そして、王に相応しきワインを飲むことを教えたとの女を呪詛するのか。彼女は壮麗なる着物を汝に着せ、栄光あるギルガメシュを汝の道連れとさせなかったというのか(訳注:エンキドゥは当初、神よりギルガメシュを討伐するために送られた存在であったが、神殿娼婦に篭絡される中で人間性に目覚め、かつ、ギルガメシュの友になった、そういう設定が付された獣人といった存在である)。汝自身の莫逆の友たるギルガメシュは王族の寝台にて汝が休むことを許さしめもし、また、王の長椅子の左に汝の休まる場を用意しなかったというのか。ギルガメシュは地にあっての姫らをして汝の足下に口付けさせるがごとくをなさしめ、いまやウルク(訳注:ギルガメシュを王として戴いていた都市国家)の全市民が汝の死を受けて嘆き悲しんでいる。汝が死したとき、ギルガメシュはその髪を汝がために伸ばすにまかせ、そして、ライオンの生皮をば被り、砂漠への放浪へと赴かんとしているのだぞ]」

(引用部はここまでとしておく)
※補足表記として
ちなみに、ギルガメシュは親友エンキドゥが没したことによって獅子の皮かぶりの狂態で野を彷徨することになったと(上の抜粋部に見るように)発掘碑文に記載されている存在であるわけだが、そも、ギルガメシュ親友エンキドゥが死亡した原因は
[女神イシュタルとギルガメシュの確執が極まったがためであった]
とも伝わっており、そちらエンキドゥ死亡の結果が[親しき者の死にて死を恐れるに至ったギルガメシュが不死を求めての旅に出た]理由であるともされている(:ここでは目立つところとしての和文ウィキペディア[ギルガメシュ叙事詩]項目の現行にての記載内容より、表記のこと ――[女神イシュタルとギルガメシュとの確執]がエンキドゥを殺しもし、獅子の皮を被ったギルガメシュの彷徨・不死を求めての旅をもたらしもしたとされること―― にまつわる部を(それが多少なりとも本稿にての指し示し事項に関わるとの認識から)引用しておくこととする。(以下、掻い摘まんでの引用をなすとして)ギルガメシュは暴君であったため、神はその競争相手として粘土から野人のエンキドを造った(写本そのものが粘土板から作られていることにも注意)・・・(中略)・・・その後、ギルガメシュとエンキドは力比べをするが決着がつかず、やがて2人は友人となり、さまざまな冒険を繰り広げることとなる・・・(中略)・・・このギルガメシュの姿を見た美の女神イシュタルは求婚したが、ギルガメシュはイシュタルの気まぐれと移り気を指摘し、それを断った。怒った女神は「天の雄牛」をウルクに送り、この牛は大暴れし、人を殺した。ギルガメシュとエンキドは協力して天の雄牛を倒すが、怪物を殺したこととイシュタルへの侮辱に神は怒り、エンキドは神に作られた存在ゆえに神の意向に逆らえず死んでしまった。ギルガメシュは大いに悲しむが、自分と同等の力を持つエンキドすら死んだことから自分もまた死すべき存在であることを悟り、死の恐怖に怯えるようになる。そこでギルガメシュは永遠の命を求める旅に出て、さまざまな冒険を繰り広げる
(以上、引用部とした))。
につき、エンキドゥの死を惹起し、ギルガメシュに不死を求めての旅に出た原因を与えたとされるイシュタルという女神がどういう存在であるかと述べれば、同女神は
[黄金の林檎を巡るパリスの審判で重要な役割を果たしたギリシャの女神アフロディテと(縁起由来の問題として)接合するとされる女神]
ともなり、また、
[エデンの禁断の果実 ――黄金の林檎との類似性を本稿にて細かくも解説してきたとの禁断の果実―― を誘惑の具に用いた蛇、そちらエデンの蛇と同様の特質を帯びていると先述のアステカ文明の蛇の神(ケツァルコアトル)と結びつくだけの特性を伴っている女神]
ともなっている(古代メソポタミアのイシュタルもアステカのケツァルコアトルも[金星の体現神格][冥府に双子の片割れを持つ存在]としての特性を共有している)ことを本稿にて先述なしてきたとの存在でもある(出典(Source)紹介の部48および出典(Source)紹介の部49および出典(Source)紹介の部61)。
となれば、
[類似存在を介して[黄金の林檎]と結びつくだけの要素を帯びている女神イシュタルとの確執] → [エンキドゥの死亡] → [友人の死を嘆き悲しみ、また、死を恐れるに至ったことによるギルガメシュの獅子の皮を被っての狂態、そして、それに次ぐ不死を求めての旅立ち]
との関係が成立していると述べられること「にも」なる(:ただし、そうした関係性にまつわる視点を介在させなくとも[ギルガメシュの不死を求めての旅]と[ヘラクレスの黄金の林檎を求めての旅]が結びつくと述べられるとの論拠らがあり、それら論拠らについてはこれより続いての段にて書き記していくこととなる)。
(補足の部はここまでとする)
次いで、
[(ギルガメシュの方に対して)ヘラクレスの方が獅子の皮を被った存在となっていることについての典拠]
を挙げることとする。
(ギルガメシュと獅子の皮被りの話に次いで同文のことがヘラクレスにも当てはまる典拠を挙げるとして)ヘラクレスが討伐したネメアの獅子の毛皮を被った存在として彫像化・描写されてきたことは先に挙げた図像らの右側、ルネサンス期絵画描写形態やその他諸々のオンライン上より確認できる遺物にて認められるヘラクレス似姿などを通じ視覚的にも容易に理解できるようになっている ――先の段にあって Hercules and the Hydraと題された15世紀絵画(ルネサンス期芸術家のアントニオ・デル・ポッライオーロ Antonio del Pollaioloの手になる作)を挙げている―― わけではあるも、同じくものことについては例えば、次のような説明がなされている。
(直下、英文Wikipedia[ Nemean lion ]項目にての The First Labour of Heracles[ヘラクレスの第一の功業]の節にあっての現行記載内容よりの掻い摘まんでの引用をなすとして)

The first of Heracles' twelve labours, set by King Eurystheus (his cousin) was to slay the Nemean lion.[ . . . ]After slaying the lion, he tried to skin it with a knife from his belt, but failed. He then tried sharpening the knife with a stone and even tried with the stone itself. Finally, Athena, noticing the hero's plight, told Heracles to use one of the lion's own claws to skin the pelt.[ . . . ] The Nemean lion's coat was impervious to the elements and all but the most powerful weapons. Others say that Heracles' armour was, in fact, the hide of the lion of Cithaeron.
(訳として)「エウリュステウス王(ヘラクレス親戚たる王)よりヘラクレスに申し渡されたヘラクレス12功業のうちの最初のものはネメアのライオンを誅伐することであった・・・(中略)・・・同ライオンを(苦闘の末に)殺傷した後、彼ヘラクレスはベルトからナイフを取り出してその皮を剥ごうとしたが、失敗した。そこで彼は研ぎ石でもってナイフを研ぎながら、そして、研ぎ石そのものを用いながら、皮剥ぎを試しもした(が皮を剥ぐことに失敗した)。しまいには、女神アテナが英雄苦境を見かねもし、ヘラクレスにライオン自身の爪を獅子の外皮を剥ぐのに使うようにと助言した・・・(中略)・・・ネメアの獅子の皮はもっとも強力なる武器でなければ貫くことは出来ぬとのものであった。(それがため)人々は[ヘラクレスの鎧とは実際はキタイローン(訳注:ネメアのライオンが暴威を振るっていた一帯)の獅子の皮であった]としている」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)
([ギルガメシュとヘラクレスの[獅子をいなす英雄][獅子の皮かぶりの英雄]との特質]とのことにまつわっての出典(Source)紹介の部63はここまでとする)
(ギルガメシュとヘラクレスの類似性にまつわる表記を続けて)
獅子とワンセットに描かれることが多かった存在、そして、獅子の生皮を被って砂漠を放浪したとのギルガメシュについては
「バビロンの都市ウルクの王子としてウルク王と女神の子供として生を受けた」
と遺物が語っている存在、要するに、神の血を引く[半神](デミ・ゴッド)としての属性をもった存在であるとされる。
他面、獅子の毛皮を被った姿でよくも図像・彫像化されてきたヘラクレスについてもゼウスの血筋を受けての半分神の存在であると神話が語っている存在である。
冒険譚に登場を見ている神の血を受けた英雄、そういう観点でもギルガメシュとヘラクレスには接合性がある。

ここ出典(Source)紹介の部63(2)にあっては[ギルガメシュおよびヘラクレスが神の血を引いている存在(半神・デミゴット)となっていること]についての典拠紹介をなしておく。
まずもってギルガメシュが神の血を引くデミ・ゴッド(半神)であったとのことについては ――即時即座に確認できるところの―― 英文Wikipedia[Gilgamesh]項目の前半部の現行記述を引いておくこととする。
(直下、英文ウィキペディア[Gilgamesh]項目より引用をなすとして)

In Mesopotamian mythology, Gilgamesh is a demigod of superhuman strength who built the city walls of Uruk to defend his people from external threats, and travelled to meet the sage Utnapishtim, who had survived the Great Deluge. He is usually described as two-thirds god and one third man.
(訳して)「メソポタミア神話体系にてはギルガメシュはその庇護下にある民を外敵から守るためにウルクに都市城壁を築いたとの超人的な力を有した[半神](demigod)とされており、また、大洪水を生き残びたとの賢人ウトナピシュテムに会うための旅に出た存在であるともされている。彼は定例として[三分の二が神、三分の一が人間である]と形容されている存在である」

(訳を付しての引用部はここまでとする ―※― )
(※同じくもの点に関して和文ウィキペディアでは ―[ギルガメシュ叙事詩]項目にての現行記述内容より原文引用するところとして― ウルクの王ギルガメシュは、ウルク王ルバルバンダと女神リマト・ニンスンの間に生まれ、3分の2が神で3分の1が人間と言う人物であった
(引用部はここまでとする)と表記されている。それにつき基本的なことなのでたかだかものウィキペディア程度の媒体よりの引用にとどめたが、引用部記述については[その通りとされている]ことにつき、折り紙を付ける、(内容が散漫としていて引用なしづらいところながらも)ギルガメシュ叙事詩の内容につき、和文・英文双方で具体的中身の検討をなしている(その点からして疑わしきにおかれては出典(Source)紹介の部60の内容などを確認されたい)人間として折り紙を付ける次第である)
他面、ヘラクレスが「半分神」の存在であったと伝わっていることについては同じくも英文Wikipedia[Hercules]項目程度のものから引くだけで十分かと判断、そうしておくこととする。
(直下、英文ウィキペディア[Hercules]項目より引用をなすとして)

Hercules is the Roman name for the Greek divine hero Heracles, who was the son of Zeus (Roman equivalent Jupiter) and the mortal Alcmene.
(訳として)
「ハーキュリーズとは[(ローマにてのジュピターたる)ゼウス神]と[死せる運命を背負った(人間の)アルクメネ]の子であったギリシャの神聖帯びての英雄ヘラクレスのローマ語呼称となる」

(引用部に対する訳はここまでとしておく ―※― )
(※につき、ヘラクレスが浮気してのゼウス神と人間のアルクメネとが設けた子供となっていたことにゼウス神の妻たるヘラ神が悋気(嫉妬心)を催しもし、赤子の折のヘラクレスを殺さしめるために蛇らを送りつけたが、逆にその蛇らが怪力の赤子ヘラクレスにくびり殺されることになったとのことはよく知られた神話上の一挿話となっているとのことがある―― )
(出典(Source)紹介の部63(2)はここまでとする)
ここまでにて
[ギルガメシュとヘラクレスの間には[[ビジュアル面]含めての存在としての特性]に共通性が見てとれるようになっている]
とのことについての典拠紹介をなし終えたとして (一言要約すれば、ビジュアル的にギルガメシュもヘラクレスも[獅子を易々といなす存在]として視覚描写され、伝承文言とのことで言えば、双方共々、[獅子の皮を被った存在][半分、神の血を引く存在(半神;デミゴッド)]として伝わってもいるとのことにつき示したとして) 、 これよりさらに指摘するところの類似性、
[伝承に見る、ギルガメシュ・ヘラクレスの両存在の「特定の」冒険とその冒険にての取得目標物にあって顕著な多重的類似性がみとめられるようになっている]
との側面が ―その[できすぎ具合]と[意味性]より― 本来ならば等閑に付すべきではないところであると強調するところとなる。
さて、それこそが問題となると強調したいところの、
[伝承に見る、ギルガメシュ・ヘラクレスの両存在の「特定の」冒険とその冒険にての取得目標物]
に関しては
[ギルガメシュとヘラクレスが(特定の冒険にて)それぞれ同じくも「大洋を渡って」[地の果て]に赴いた ―大洋の先にあっての辺土に赴いた― と述べられること]
[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険対象地に[洪水伝承]と結びつくとの側面を伴っていること]
[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)取得目標物に不死と結びつくとの側面が伴っていること]
[ギルガメシュ・ヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険目標物を巡って爬虫類の存在との衝突が生じているとの側面が伴っていること]
との各要素がみとめられもするようになっている (要するに、である。彼らの特定の冒険 ―すぐに出典紹介部にあって言及するが[ギルガメシュの不死を求めての冒険]と[ヘラクレスの黄金の林檎を求めての第11功業]ら― は多重的に際立っての類似性を帯びているということである)。
それでは以下、表記のことについての典拠紹介を順を追ってなしていくこととする。

ここ出典(Source)紹介の部63(3)にあっては
1.[ギルガメシュとヘラクレスが(特定の冒険にて)それぞれ同じくも「大洋を渡って」[地の果て]に赴いた ―大洋の先にあっての辺土に赴いた― と述べられること]
2.[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険対象地に[洪水伝承]と結びつくとの側面を伴っていること]
3.[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)取得目標物に不死と結びつくとの側面が伴っていること]
4.[ギルガメシュ・ヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険目標物を巡って爬虫類の存在との衝突が生じているとの側面が伴っていること]
との各要素がみとめられることについての典拠紹介を順々になしていくこととする。
まずもっては
1.[ギルガメシュとヘラクレスが(特定の冒険にて)それぞれ同じくも「大洋を渡って」[地の果て]に赴いた ―大洋の先にあっての辺土に赴いた― と述べられる]
とのことの典拠紹介をなすこととする。
同じくものことに関しては本稿にての先の段でもその内容を引いて問題視してきたところのジェームズ・フレーザー(一個の学問領域を呪術信仰に対する分析を通じて開拓していったともされる学究)の手になる著作、 Internet Archiveのサイトなどオンライン上より誰でもそのPDF版をダウンロード可能となっているとの、
Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law(同著、直訳すれば、『旧約聖書に見る伝承:比較対象としての宗教・伝承・法則にまつわる研究』とでも訳されよう著作となり、うち、[世界中の洪水伝承を蒐集・紹介・分析したパート]が完訳版ではなく、そこだけ切り取っての訳がなされてとの抄訳版『洪水伝説』として国内でも刊行されている(版元は国文社という出版社)との著作となる)
からの原文引用をなすこととする。
(直下、オンライン上にて確認可能なる1918年著作権表記がなされての FOLK-LORE IN THE OLD TESTAMENTのp.112-p.113よりの引用をなすとして)

The hero of the poem, Gilgamesh, has lost his dear friend Engidu by death, and he himself has fallen grievously sick. Saddened by the past and anxious for the future, he resolves to seek out his remote ancestor Ut-napishtim, son of Ubara Tutu, and to inquire of him how mortal man can attain to eternal life. For surely, he thought, Ut-napishtim must know the secret, since lie has been made like to the gods and now dwells somewhere far away in blissful immortality. A weary and a perilous journey must Gilgamesh accomplish to come at him. He passes the mountain, guarded by a scorpion man and woman, where the sun goes down: he traverses a dark and dreadful road never trodden before by mortal man : he is ferried across a wide sea: he crosses the Water of Death by a narrow bridge, and at last he enters the presence of Ut-napishtim.
(拙訳として)
「英雄叙事詩にてギルガメシュは彼の親友エンキドゥを失い、重大な心の闇を抱えることになった。過去あったことへの悲嘆、そして、将来に対する憂えから彼は彼の遠い祖先にあたる男、ウトナピシュティム ―ウバラ・トゥトの息子― を探し求め、そして、彼にいかにして死すべき運命を背負った人間が永遠の命を得ることができるのか問う、とのことをなさんと考えた。の際、疲弊・苦難に満ちた旅の全うが成し遂げるべくものとしてギルガメシュに求められ、彼は蠍男(スコーピオン・マン)と蠍女に守られた日の沈むところの山を越え、従前、死すべき運命の人間に踏破されたことなき暗く恐ろしい道を横切った。そして、彼は大洋を船で通過、狭き橋を渡って[死の水]の領域を越え、遂にウトナピシュティムのいるところにまで辿り着いた」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
端的にまとめれば、ギルガメシュは「死すべき運命の人間にかつて踏破されたことなき道を越え」そのうえで「大洋を越えて( he is ferried across a wide sea )」目的物に到達している(との内容の粘土版が出土している)。
換言すれば、それは
[未踏の辺土としての海の果て](にある大洪水を生き残った者の領域)
に辿り着いたとのことである。
以上、ギルガメシュの不死を求めての冒険に対して、
[ヘラクレスの[ヘスペリデスの黄金の林檎の園]を求めての冒険 ――英文Wikipedia[ Labours of Hercules ]項目にての[ Eleventh Labour: Apples of
the Hesperides ]の節にて現行、 After Hercules completed his first ten Labours, Eurystheus gave him two more claiming that neither the Hydra counted (because Iolaus helped Hercules) nor the Augean stables (either because he received payment for the job or because the rivers did the work). The first of these two additional Labours was to steal the apples from the garden of the Hesperides.
(訳として)「ヘラクレスが(当初それだけこなすことを求められていた)10の功業を終えた時、エウリュステウス王は「ヒドラ退治(の功業)はイオラオスからの助力を受けたために無であり、アウゲイアースの家畜小屋(の掃除の功業)は仕事の対価に報酬を受けている、あるいは、川の流れをもってして助けとしたために無である」と主張しつつも彼にさらに二つの功業を課した。それら追加の功業(第11功業と第12功業)のうちの最初のものはヘスペリデスの園から(黄金の)林檎を掠め取ってくるように、とのものであった」(訳付しての引用部はここまでとする)と記載されているとおりの第11功業―― ]
に関して「も」同文のことが述べられていたとのことがある。
以下を参照されたい。
(直下、 Project Gutenbergのサイトにて公開されている(すなわち現行、誰でもインターネットを介して閲覧できるようになっている)19世紀末の講演(Lecture)記録としての Prehistoric Structures ―OF― CENTRAL AMERICA. WHO ERECTED THEM?『先史時代の中央部アメリカの構図。誰がそれらを作図したのか』( Martin Ingham Townsendという弁護士にして政治家であったとの人物に由来する講演録)よりの引用をなすとして)

2. Let us look for a moment at some of the things which the ancient Greek and Latin authors have said indicating their knowledge of the existence of a western continent. Crates, a commentator on Homer, is quoted by authority of Strabo, a very learned author of the century before Christ, as saying that Homer means in his account of the western Ethiopians the inhabitants of the Atlantis or the Hesperides, as the unknown world of the west was then variously called.
(急場を縫っての拙訳として)
「少しの間、古代ギリシャと古代ラテン世界の著述家らが[西方の大陸]の存在にまつわる彼ら知識を示しての物言いをなしていたとのことにまつわってのいくばくかのところに目を向けてみよう。クレイトス、ホメロスの注釈家たる同クレイトス(
Crates of Mallus )についてはキリスト生誕以前にてとてつもなく識見が深いことで知られていたストラボンの権威ある筆によるところとして、「エチオピア西方に対する説明としてホメロスが意味せんとしているのは様々な呼称で呼ばれているところの未知の世界としての[アトランティス]あるいは[ヘスペリデス(の園)]の住民のことである」と述べていた(と伝わっている)」)

(訳を付しての引用部はここまでとしておく)
(続いて直下、同じくも Project Gutenbergのサイトにて公開されている20世紀初頭にて世に出た STORIES OF OLD GREECE AND ROME(1913)との著作よりの引用をなすとして)

When the ancients looked each evening at the glowing west, they pictured it as a far-distant country, more wonderful than any ever seen by mortal eyes. Here in this land of heart's desire lay the Garden of the Hesperides, where a dragon guarded the golden apples that grew on a wonderful tree which had sprung up miraculously to grace the wedding of Jupiter and Juno. In this far-off sunset land were also the Isles of the Blest,where mortals who had led virtuous lives were transported without ever tasting of death.
(急場を縫っての拙訳として)
「古代人は(黄昏時にて)輝く西方に目を向けた折、そこに[死すべき定めを追った人間の目(モータル・アイズ)が見ることができるなによりも素晴らしきものたる,遙か彼方の地]を描いていた。といった中、心中の渇望の地の中心に横たわっていたのが[ジュピター(ゼウス)とユーノー(ヘラ)の婚姻を祝すものとして奇跡の如く急成長したとの不思議の樹に実るとの黄金の林檎、その黄金の林檎の番を竜がしているとのヘスペリデスの園]であった。この遙か日の沈む先にある島は[祝福の島]、有徳の生を送っても生ある者らが「死の味をかみしめることなくしては」そこに至れないとの地ともされていた」

(訳を付しての引用部はここまでとしておく ―※― )
(※尚、[ヘスペリデスの園]については先行するところの出典(Source)紹介の部40の部に続けての段、そこにての注記の部にて紹介しているように[キュレネ](注:リビアに建設された元ギリシャ系植民都市)あるいは[ベンガジ](注:これまたリビアに建設された元ギリシャ系植民都市)の近傍ないし世界を取り囲むオケアノス(注:古代ギリシャの世界観にあっての世界を取り囲む大洋)の縁にあるとの見立てが存していたとのこともあるのだが、といった中で以上、引用なしたような見方が呈されてきたとのことがありもする)
上のことから航海描写がよくもなされてのヘラクレスの黄金の林檎の園への旅路は
[大海の先に向かっての辺土を目指してのプロセス]
とも言い換えられるようになっている。
(:ヘスペリデスの園へ向かうための大洋渡航とのことで述べれば、本稿の先の段で Project Gutenbergのサイトを通じてもダウンロード全文ダウンロード可能となっているところのブリタニカ百科事典の最も著名なる版、 Encyclopaedia Britannica, 11th Editionより次の表記を引いていたところに通ずることともなる。(以下、 Encyclopaedia
Britannica, 11th Edition, Volume 13にてのHesperides項目よりの再度の引用をなすとして) HESPERIDES,
in Greek mythology, maidens who guarded the golden apples which Earth gave
Hera on her marriage to Zeus. According to Hesiod (Theogony, 215) they
were the daughters of Erebus and Night; in later accounts, of Atlas and
Hesperis, or of Phorcys and Ceto (schol. on Apoll. Rhod. iv. 1399; Diod.
Sic. iv. 27).[ . . . ] They lived far away in the west at the borders of Ocean, where the sun
sets. Hence the sun (according to Mimnermus ap. Athenaeum xi. p. 470) sails
in the golden bowl made by Hephaestus from the abode of the Hesperides
to the land where he rises again.
(幾分か委細省いての訳として)「ヘスペリデスはギリシャ神話にて大地神が女神ヘラのゼウスとの婚礼に際して贈り与えた黄金の林檎を守護する乙女らとなる。ヘシオドス『神統記』によれば、彼女らはエレボス神と夜(の体現神格)の娘らであるとされ、より後の説明では、アトラスおよびヘスペリス神の娘ら、あるいは、ポルキュスとケートーの両神の娘らであるとされている(ロドス島のアポロニウスらの言いようの特定部による)。・・・(中略)・・・彼女らは[遙か西方の大洋の果て]、[日が沈むところ]にて住まうとされる(注:言うまでも無いことかとは思うが、日は東から昇って西に沈む)。それゆえに、(ミムネーマスによる古典によれば)太陽はヘパイトスにて鋳造された黄金の鉢状の容器にはいっての形にてヘスペリデス住まいから彼が再び昇る場へと航海をなしていくとされている」(訳を付しての引用部はここまでとする))
ここまでにて
1.[ギルガメシュとヘラクレスも「特定の冒険にて」それぞれ同じくも大洋を渡って地の果てに赴いたと述べられる]
とのことの典拠紹介とした。
次いで
2.[ギルガメシュ・ヘラクレス双方の特定の冒険にての冒険目標物が洪水伝承との結びつく]
とのことの出典紹介をなすこととする。
ギルガメシュが不死の秘密を探るために会いに行ったウトナピシュティム(ギルガメシュに不死の霊薬 ―若返りの草(ないし草状の珊瑚)― の場所を教えた存在)が[大洪水の生き残り]であるとされることについては本稿出典(Source)紹介の部60の部で次のように出典紹介をなしていたとおりである。
(直下、『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)p.135にてのギルガメシュ叙事詩を収めた碑文のうち、第11の書版と振られた出土碑文の内容の要約を扱った箇所(発掘碑文の和訳を書籍で提示しているとの学究が日本語で解説をなしているとの部)より「再度の」原文引用をなすとして)

[ギルガメシュの懇望にまけて、ウトナピシュテムは自分が神々に列せられた経緯を語って聞かせる。神々が人間を滅ぼそうとして地上に洪水を送ったとき、知恵の神エアの指示により、彼は方舟を建造し、地上のすべてを粘土に帰した洪水からいのちあるものの種を救ったが、洪水を起こしたエンリル神はそれを知って怒った。しかし、最後は、エアに説得され、彼に神々のような不死を与えたのである、と。この後、ウトナピシュテムはギルガメシュに、七日間、寝ずにいる試練を課すが、ギルガメシュはこれに耐え得ない。ウトナピシュテムはギルガメシュを自分の町に送り返そうとする。ところが、同情あふれる妻の言葉があり、ウトナピシュティムはギルガメシュに「若返りの草」のありかを教える]

(引用部はここまでとする)
(続けて直下、 THE EPIC OF GILGAMESH A NEW TRANSLATION『新訳版ギルガメシュ伝承』(イギリスの老舗出版社ペンギン社より出されている Penguin Classics版、 Andrew R. Georgeというバビロニア学の権威との学者によって訳が付されているバージョン)にあっての Tablet XI. Immortality Denied(第11碑文要約、[拒否されし不死])の部よりの「再度の」引用をなすとして)

Gilgamesh asks Uta-napishti how he gained eternal life, and hears how Utanapishti survived the Deluge and was given immortality by the gods as a result. Uta-napishti suggests Gilgamesh go without sleep for a week. Gilgamesh fails the test and realizes in despair that if he cannot beat Sleep he has no hope of conquering Death.
(訳として)「ギルガメシュはウトナピシュテムに彼がいかようにして不死を得たのかを尋ね、彼がどのように「洪水」を生き延び、そして、結果として神々に不死を与えられたのかを聞くこととなった。ウトナピシュテムはギルガメシュに睡眠を取らずに一週間を過ごすことを(不死を得るための試練として)課した。ギルガメシュはこの試練を成し遂げるに失敗し、眠りさえも克服できぬというのならば、死を克服する希望なぞおよそもちえまいと失意のうちに悟ることになる」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
以上をもってギルガメシュ冒険 ――第11の石版 Tablet XIと学者らに銘打たれている粘土版に描かれている冒険―― が洪水伝承と結びついていることを示す典拠とした。
他面、ヘラクレスがその第11功業にて求めた黄金の林檎の園たるヘスペリデスの園 ――アトラスの一群の娘達(アトランティデス)に属するヘスペリデスの管理管掌する大海の果ての領域―― が
[アトランティス]
に同定され、そのアトランティスが洪水で滅していると伝わっている存在であることにまつわる典拠を挙げておく。
につき、ヘラクレスの黄金の林檎を求めての冒険の目標地(ヘスペリデスの園)が[アトランティス]と結びつくとされてきたものであるとの点については本稿の先の段、出典(Source)紹介の部41以降の段にての一連の解説部で説明を講じてきた。につき、たとえば、本稿出典(Source)紹介の部41では Project Gutenbergなどのサイトを通じて現行、全文ダウンロードできるようになっているとの19世紀後半から20世紀初頭にかけて物議を醸していた著作 Atlantis: The Antediluvian World『アトランティス大洪水前の世界』(1882)にての CHAPTER VIII.THE OLDEST SON OF NOAHの章、そのp.453よりの抜粋として(以下、再度の引用をなすとし) Agriculture.--The Greek traditions of "the golden apples of the Hesperides" and "the golden fleece" point to Atlantis. The allusions to the golden apples indicate that tradition regarded the "Islands of the Blessed" in the Atlantic Ocean as a place of orchards. And when we turn to Egypt we find that in the remotest times many of our modern garden and field plants were there cultivated.
(拙訳)「農業について――[ヘスペリデスの園の黄金の林檎]および[金羊毛皮]にまつわるギリシャ伝統はアトランティスの方向を指し示すものである。黄金の林檎に対する言及は果樹園の場としての[大西洋の祝福されし島]にまつわる伝承のことを想起させる。そして我々がエジプトに立ち戻った時、往古にて我々の今日の果樹園や栽培種の多くがそこにて栽培されていたことを見出すのである(訳注:ここでは『アトランティス大洪水前の世界』著者イグナティウス・ドネリーはアトランティスとして同定できるものがギリシャら欧州やアメリカ先史時代に農業的な影響を与えていたとの式での申しようをなしている)」(再度の引用部に対する訳はここまでとする)といった記述を引いたりもしていた次第である ――ちなみに本稿筆者は Atlantis: The Antediluvian Worldの内容を「言論流通動態の問題」として引きもしもするが、その著者たるイグナティウス・ドネリーの主張を全面的に容れているわけでもなく、また、イグナティウス・ドネリー主張が正しかろうとそうでなかろうと本稿の内容には影響を与えることでもないと従前の段より断っている( my point of view: Whether viewpoints seen in ATLANTIS THE ANTEDILUVIAN WORLD ( by Ignatius Loyola Donnelly's ) are proper or not, it makes no differnce.と断っている)ことも一応、付記しておく―― )。
対して、アトランティス ――直上にて再言及のようにヘラクレスが探し求めていた[黄金の林檎の栽培地ヘスペリデスの園]にも仮託される場―― が洪水で滅尽を見たとされることについては先の出典(Source)紹介の部36の段にて次の通りの引用をなしているとおりである。
(直下、プラトン全集12(岩波書店刊行)『ティマィオス』収録部のp.22―p.23より以下、中略をなしつつもの「再度の」引用をなすとして)

というのは、あの大洋には――あなた方の話によると、あなた方のほうでは「ヘラクレスの柱」と呼んでいるらしいが――その入口(ジブラルタル海峡)の前方に、一つの島があったのだ。そして、この島はリビュアとアジアを合わせたよりもなお大きなものであったが、そこからその島の他の島々へと当時の航海者は渡ることができたのであり、またその島々から、あの正真正銘の大洋をめぐっている、対岸の大陸全土へと渡ることができたのである。
・・・(中略)・・・
さて、このアトランティス島に、驚くべき巨大な、諸王国の勢力が出現して、その島の全土はもとより、他の多くの島々と、大陸のいくつかの部分を支配下におさめ、なおこれに加えて、海峡内のこちら側でも、リビュアではエジプトに境を接するところまで、また、ヨーロッパではテュレニアの境界に至るまでの地域を支配していたのである。実にこの全勢力が一団となって、あなた方の土地も、われわれの土地も、否、海峡内の全地域を、一撃のもとに隷属させようとしたことがあったのだ。
・・・(中略)・・・
しかし後に、異常な大地震と大洪水が度重なって起こった時、苛酷な日がやって来て、その一昼夜の間に、あなた方の国の戦士はすべて、一挙にして大地に呑み込まれ、またアトランティス島も同じようにして、海中に没して姿を消してしまったのであった。

(国内流通訳書よりの引用部はここまでとする ―※― )
(※尚、表記の引用部にあってのオンライン上より全文確認可能な英訳版表記は( Project Gutenbergサイトより全文ダウンロードできるとの英訳版 TIMAEUS by Plato ――19世紀にあってのオクスフォードのプラトン翻訳家となる Benjamin Jowettとの向きによって訳がなされている版―― より掻い摘まんでの「再度の」原文引用をなすとして) The most famous of them all was the overthrow of the island of Atlantis. This great island lay over against the Pillars of Heracles, in extent greater than Libya and Asia put together, and was the passage to other islands and to a great ocean of which the Mediterranean sea was only the harbour; and within the Pillars the empire of Atlantis reached in Europe to Tyrrhenia and in Libya to Egypt. This mighty power was arrayed against Egypt and Hellas and all the countries bordering on the Mediterranean.[ . . . ] A little while afterwards there were great earthquakes and floods, and your warrior race all sank into the earth; and the great island of Atlantis also disappeared in the sea. This is the explanation of the shallows which are found in that part of the Atlantic ocean.'
との部位が該当するところとなる)
ここまででもってして
2.[ギルガメシュ・ヘラクレス双方の特定の冒険にての冒険目標物が洪水伝承との結びつく]
とのことの典拠紹介とした。
(出典(Source)紹介の部63(3)を続けるとして)
次いで
3.[ギルガメシュ・ヘラクレス双方の特定の冒険にての取得目標物が[不死]と結びつく]
とのことについての典拠を紹介しておく。
ギルガメシュの目標が不死であったことについてはここまでも和訳された版の『ギルガメシュ叙事詩』の梗概部(要約部)の原文引用などを通じて何度も何度も紹介してきたことであるのでそちらを参照されたい。
(:たとえば本稿にての直上直近の部にても出典(Source)紹介の部60にてなしたところの引用を「再度」なせば、(『ギルガメシュ叙事詩』(岩波書店)p.135にてよりの原文引用として)[ギルガメシュの懇望にまけて、ウトナピシュテムは自分が神々に列せられた経緯を語って聞かせる。神々が人間を滅ぼそうとして地上に洪水を送ったとき、知恵の神エアの指示により、彼は方舟を建造し、地上のすべてを粘土に帰した洪水からいのちあるものの種を救ったが、洪水を起こしたエンリル神はそれを知って怒った。しかし、最後は、エアに説得され、彼に神々のような不死を与えたのである、と。この後、ウトナピシュテムはギルガメシュに、七日間、寝ずにいる試練を課すが、ギルガメシュはこれに耐え得ない。ウトナピシュテムはギルガメシュを自分の町に送り返そうとする。ところが、同情あふれる妻の言葉があり、ウトナピシュティムはギルガメシュに「若返りの草」のありかを教える。この草を得たギルガメシュは勇躍歓喜して、ウルクに戻ろうとするが、途中、泉の水で身をきよめている間、その草は蛇に持ち去られてしまう](引用部終端)といったことが古代碑文に記されているとされる)。
他面、ヘラクレスの求めた黄金の林檎が不死と結びつくことについては
[[「不死」の理想郷であったエデンの園]と[黄金の林檎]の結びつきを示すことが同じくものことを示すことにも通ずる]
[黄金の林檎に関しては北欧神話にての不死の飲食物としての来歴が伴っていることを示すことが同じくものことを示すことにも通ずる]
と見ているのでそれらの点についての本稿従前内容の確認を直下、なしておくこととする。
本稿出典(Source)紹介の部51では
「アメリカの先史文明がアトランティス(と呼ばれるような文明)の名残りを受けてのものである」
との異端説を展開していたとのイグナティウス・ドネリーの手になる Atlantis: The Antediluvian Worldという古書の内容を引き、そのうえで同著作にて紹介されているとの往時(19世紀)、令名を馳せていた歴史学者(英文Wikipediaにも一項設けられているとのアレギザンダー・ムーレイ Alexander Murray)の手になる Manual of Mythologyとの著作 ―著作名の検索エンジン上での入力で内容が容易に確認可能となっている著作― の次のような記述を引いていた。
(直下、 Manual of Mythologyよりの再度の引用をなすとして)

The Gardens of the Hesperides with the golden apples were believed to exist in some island in the ocean, or, as it was sometimes thought, in the islands on the north or west coast of Africa. They were far-famed in antiquity; for it was there that springs of nectar flowed by the couch of Zeus, and there that the earth displayed the rarest blessings of the gods : it was another Eden.
(訳として)「黄金の林檎が実るヘスペリデスの園は大洋にあってのどこかの島に存在する、あるいは、アフリカ沖から北ないし西に向かった先にあると考えられている。そこは古典古代の時代にあって[ゼウス寝所のそばにて流れるネクター(神々の不死の飲料のこと)の発する場]にして[この地上にあって神々の最も得がたき祝福が施された場]として非常に有名であった。すなわち、ヘスペリデスの園はもう一つのエデンであった」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
上の記述よりお分かりだろうが、[黄金の林檎の園]は
[人間(人の始祖たるアダムとイヴ)がそこより追放されたために不死を失ったともされる、[不死を約束する生命の樹]と[知恵の樹]の実が実っていた場としてのエデンの園]
と結びついているとされる ――(本稿出典(Source)紹介の部54にてもそこよりの引用なしたとの日本聖書協会『旧約聖書』創世記第3章22-24節よりの再度の原文抜粋をなすとして)[主なる神は言われた、「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない」。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が造られたその土を耕されせらた。神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと、回る炎のつるぎを置いて、命の木の道を守らせた](聖書よりの引用はここまでとする)との言われようのエデンの園と結びついているとされる―― との観点で「まずもって」不死と結びつく。
また、ヘラクレスが求めた黄金の林檎については[不死の桃源郷たるエデンの園]との関係性だけではなく、北欧神話にて
「女神イドゥン(イズン)が管理する神々を老いから解放し、彼らに不死を約する食物]
として登場するようなものであることもあり、それがゆえ、
[多重的に不死の関係が想起されるようになっているもの]
ともなる。
北欧神話の不死の象徴たる林檎を管掌する女神イドゥンについては
(直下、目に付くところの英文Wikipedia[Iðunn]項目の現行記載より「まずもっての」引用をなすとして)

In Norse mythology, Iðunn is a goddess associated with apples and youth.Idunn is attested in the Poetic Edda, compiled in the 13th century from earlier traditional sources, and the Prose Edda, written in the 13th century by Snorri Sturluson.
「北欧神話にてイドゥンは林檎および若さと関連する女神である。彼女イドゥンはより時代遡ってのところで13世紀編集となっている『詩文エッダ』にてその存在が示されている女神、そして、13世紀にスノッリ・ストゥルルソンによってものされた『散文エッダ』にあってその存在についての記載がなされているとの女神となる」

(引用部はここまでとする)
と記載されているといったかたちでよく知られる存在となっている。
その点、北欧神話にあっての[不死を約束する黄金の林檎]の登場例については
[[オーディンの魔法の指輪ないし腕輪:リング・ドラウプニル]と結びつけられる[黄金の林檎]]
について本稿にての先の段、便宜的に出典(Source)紹介の部60(3)と振った段でも言及をなしていたところでもある。
具体的には Project Gutenbergにて誰でも入手できるとのH. A. Guerberという前世紀前半まで活動の英国人史家の手になる Myths of the Norsemen From the Eddas and Sagas、『エッダからサガに至るまでの北欧人種の神話』とでも訳せよう同著作にての The Wooing of Gerda[ゲルズへの求婚]との節にあっての『スキールニルの歌』というエッダ収録詩にての解説部より
(直下、 Project Gutenbergサイトにて公開の著作、 Myths of the Norsemen From the Eddas and Sagasよりの「再度の」引用をなすところとして)

To induce the fair maiden to lend a favourable ear to his master’s proposals, Skirnir showed her the stolen portrait, and proffered the golden apples and magic ring, which, however, she haughtily refused to accept, declaring that her father had gold enough and to spare.
「(スキールニルが自身が北欧の神フレイの恋の仲介役を演じることになったとのその相手方の巨人族の乙女ゲルズの説得に際し)輝く金髪の乙女の耳をば自分の主人の提案へと傾けさせるため、スキールニルは主人の肖像を見せ、そのうえで、[黄金の林檎]と[魔法のリング]を(彼女がフレイ神と結ばれる対価に、と)提示したが、彼女は[彼女の父は十分にして余りあるほどの黄金を持っている]とたからかに述べ、その申し出を容れることを拒んだ」

(訳を付しての引用部はここまでとする)
との記述(解説)がなされていることを(脇に逸れての話の中で)取り上げてもいた。
さて、同『スキールニルの歌』では
[「11の」黄金の林檎](ヘラクレスの功業でも第「11」功業が黄金の林檎を求めてのものとなっていること、本稿にて何度も言及してきた)
が
[魔法の指輪ないし腕輪(ドラウプニル)]
と共に恋の仲介役たるスキルニルによって乙女ゲルズに[フレイヤとの婚姻対価]として提示されていたと叙述されているとのことが極一部の北欧神話研究者の間で知られているとのことがある。
につき、『スキールニルの歌』は「和訳版の」北欧神話エッダ紹介書籍にも収録されているものとなり、当該訳書、新潮社より出されているとの『エッダ ――北欧歌謡集』(初出1973年.訳者は北欧文学を専攻していたとのことである谷口幸男元広島大学教授)にあっての『スキールニルの歌』注釈部には次のような記載がなされている次第である。
(直下、筆者が探求の一環として読したところの『エッダ ――北欧歌謡集』(新潮社,1973年刊)p.67、『スキールニルの歌』注釈にあっての部より原文抜粋するところとして)

[林檎を十一:十一という数はおかしい。九が古代ゲルマンでの神聖な数である。 epli ellifo林檎を十一は、 epli elle-lyf若返りの林檎の書き誤りではないかという説がある。スノリの「ギュルヴィたぶらかし」にもあるように、ブラギの妻イズンは、神々が年をとったときに食べる若返りの林檎をとねりこの箱にしまっている。イズンの黄金の林檎について九世紀のスカルド詩人スィヨゾールヴ・オール・フヴィーニが書いているものによると、イズンはあるとき、その林檎ともども、ロキのために、巨人スィアチの手におちた。アース神は年をとりはじめ、ロキはイズンと林檎をとり戻さねばならなかった。彼は鷹の姿に身を変えて巨人の国へ飛び、イズンを胡桃(くるみ)に変えて首尾よくつれかえった]

(引用部はここまでとする)
上に見るように、
[[若返りの林檎]と結びつけられる北欧神話にあってのイズン(イドゥン)の[黄金の林檎]が[11]という数と結びつけられて『スキールニルの歌』に関わるところとして登場を見ている]
と国内の北欧文学研究者に解説されているようなことがある (:さらに述べれば、『エッダ ――北欧歌謡集』(新潮社より1973年にてより刊行)にての表記引用部では[[11]という数はゲルマンの神聖なる数[9]「ではない」ので、『スキールニルの歌』に見る黄金の林檎と[11]の結びつき( epli ellifo )は[若返りの林檎]( epli elle-lyf )の誤りではないのかとの説もある]と北欧文学研究者(谷口幸男元広島大学教授)にあって言及されているとのことにつき、のようなことをくだくだと言及・解説しているのは筆者が訓詁学などといったものに興味・関心があるからでは毛頭なく、先の「9」「11」の事件の発生を「どういうわけなのか」事前言及しているが如く特定文物が存在しており、それらが[黄金の林檎]とも密接に関わっているとの知識があるからである ――うち一例については既に出典(Source)紹介の部37から出典(Source)紹介の部37-5にて解説してきた―― ) 。
上のこと、北欧神話関連の古エッダ収録詩にあって黄金の林檎が11と結びつくことはヘラクレスの黄金の林檎を求めての冒険が[第11番目の功業]( the eleventh labour of Hercules )となっていることと平仄が合いもすることである(:無論、それだけ述べれば、こじつけがましきことになるところでもあるが、同じくもの件が先に発生した911の「予見」事象らといかに多重的に関わっているのか、それがゆえにいかに問題になるのか、とのこと「も」本稿の後の段で具体例挙げ連ねながら事細かな解説をなしていく所存である)。

上掲図は
[北欧神話にて黄金の林檎を管掌する女神イドゥン]
および
[イドゥンを取り巻く北欧神話上の存在]
を挙げたものとなる。
図にあっての上の段では John Bauerという画家によって描かれた20世紀初頭の画(1911年作成の著作権の縛り無くWikipediaに公開されているとの画でイドゥンとイドゥン伝承に関わってくるロキ(別表記:ロプト)が併せて描かれているとの画)よりの抜粋をなした。
図にあっての下の段では Project Gutenbergのサイトにて全文閲覧・ダウンロード出来るとの書、スウェーデン人著述家 Viktor Rydbergの手になる Teutonic Mythology(『チュートン人の神話』/1889)との著作に掲載されているとの画([イドゥンの黄金の林檎を欲した巨人スゥアチとロキ(ロプト)の中空上でのやりとりを描いたもの])を挙げたものとなる(:下段の画に見るような局面にて怪鳥に変じたスィアチという巨人によって「黄金の林檎を取ってくるように」と北欧神話の騒動誘発者(トリックスター)として知られる神たるロキが脅されたと伝承は語り継いでいるところとなっている ――表記著作( Teutonic Mythology )にて Thjasse was known as the storm-giant who having been born in deformity was ever seeking golden apples from Idun to cure his ugliness. Upon one occasion assuming the form of an eagle he interrupted a feast of Odin, Honer and Loke and when the latter attempted to strike the voracious bird with a stake found himself fastened to both stake and eagle and was borne away shrieking for mercy. Thjasse promised to release Loke if he would bring to him Idun and her golden apples.[ . . . ]Idun, who possesses "the Asas' remedy against old age," and keeps
the apples which symbolise the ever-renewing and rejuvenating force of
nature, is carried away by Thjasse to a part of the world inaccessible
to the gods. The gods grow old, and winter extends its power more and more
beyond the limits prescribed for it in creation.
(拙訳として)「スィアチはゆがみをもったかたちで生まれ落ちたとの嵐の巨人となり、彼は自身の醜さを取り除くためにイドゥンから黄金の林檎を求めようとしたとの存在となる。ある機会にてそのスィアチがオーディン・ヘーニル・ロキらの供宴を鷲の姿にて遮らんとした折、三者の内のロキがその貪欲なる(鷲の姿に変じたスィアチであったとの)鳥を棒にて打ち払おうとした際、その棒諸共、鷲にくくりつけられるかたちで連れ去られる格好となりもし、(空中にて)金切り声にて慈悲を請うことになった。スィアチはもしロキが彼の元にイドゥンおよび彼女の黄金の林檎を持ってくれば、解放してやろうと請け合った・・・(中略)・・・イドゥン、[アサ神族(アース神族)の老いに抗する対処策]を保持し自然にての絶えず産まれ変わる力、若返る力を象徴しての林檎を管理していたとの彼女がスィアチによって神々の到達不可能なる世界へと略取されることになる。神々は老いはじめ、自然創造の理にて規定されていた上限を超えて冬がその勢威を強めていくことになる」(訳はここまでとする) と記載されている―― )。
画のロキと巨人のやりとりに見るように北欧神話では[黄金の林檎]がときに争いの元となっていると描写されながら、
[神々に不死を約する果実]
として神話上の存在ら、神々ら・巨人らに非常に重要視されているところとなっている(:黄金の林檎を失うと途端に神々は老化することになると伝承が語り継いでいることとワンセットである。その点、巨大な猛禽類に姿を変じたスィアチにイズンと黄金の林檎を奪われた際にも(上にての Teutonic Mythology『チュートン人の神話』と題された著作よりの引用部に見るように)神々は急激に老化し始めたと描写されている)。
そうした不死を約するもの、神にとり欠かすことの出来ぬ常食としての[黄金の林檎]と同文に[エデンの林檎]が
[悪魔らにとっての依存の対象]
となっているさまが描かれているのがミルトン『失楽園』であるとのことをも本稿の先の段にては解説していた(『失楽園』にて[誘惑に用いられた林檎]がそれを誘惑に用いた悪魔にとっての[欠かせぬ依存の対象]となっているとの描写が認められるとのことについては本稿にての出典(Source)紹介の部54(2)でも該当部原文引用にて指し示しているところである)。
そういった意味合い「でも」[黄金の林檎]と[エデンの果実]とは同質性・連続性を呈している ――(そうした意味合い「でも」としている点について「でも」付きの原因となるところ、[[黄金の林檎]と[エデンの禁断の果実]とがいかように多重的に結びつくのか]については本稿にての先の段、出典(Source)紹介の部48から出典(Source)紹介の部54(4)を包摂する長大な解説部にあって[パリスの審判や複数神格にまつわる一致性問題]についてのこととして詳説に次ぐ詳説を加えてきたとの経緯もある)―― 。
そうもした[黄金の林檎]は北欧神話あらためギリシャ神話では
[ヘラクレス11番目の功業にての目標物]
にして
[トロイア崩壊の元凶]
となっているとのものともなり(出典(Source)紹介の部39がその史料上の典拠紹介部となる)、「かてて加えて」(性質悪きことが加わってのところとして)、同[黄金の林檎]、先述のように
[911の事件に関連する事物ら]
と複合的に結びつくとのもの「とも」なっているとのものでもある(その点に関しては本稿にてのさらに続いての段で関連するところの話をさらにさらに突き詰めてなしていく所存だが、本稿にての出典(Source)紹介の部37から出典(Source)紹介の部37-5を包摂する解説部で「まずもって」「差しあたり」言及していたところとして[黄金の林檎]との副題を持つ小説が奇怪極まりない多重的な意味での911の事前言及小説となっていることについての摘示をなしてきたとのことがある)。
また、[黄金の林檎]については(本稿にての出典(Source)紹介の部35から出典(Source)紹介の部36(3)を包摂する解説部にてはじまり、本稿にての出典(Source)紹介の部46を包摂する部位に至るまで関連するところにつき解説しているように)[粒子加速器を巡る問題]([ブラックホール生成を巡る問題]でもいい)とも複合的に結びついているとのことが摘示できるようになっているとの果実「とも」なる ――再三再四強調するが、個人の属人的目分量の問題など一切関係ないところで「911にまつわる奇怪なる予見事象とも結びついている」との[黄金の林檎]は[加速器実験]とも「その動機・意図が当然に問題になろうところで」との按配で「複合的に」結びついている・結びつけられていると摘示できてしまうところの伝説上の存在となっている(そうしたことの意味性・露骨に窺えるところの動機について突き詰めんとしているのが本稿である)―― 。
(図解部はここまでとする)
(直近までの図解部が長くなったが、)
これにて
3.[ギルガメシュ・ヘラクレス双方の特定の冒険にての取得目標物が[不死]と結びつく]
とのことについての典拠紹介を終える。
出典紹介を続け、次いで、
4.[ギルガメシュおよびヘラクレスの特定の冒険にての冒険取得目標物 ――それぞれ洪水伝承と結びつく要素を伴っている[不死の草]と[黄金の林檎]―― に[爬虫類絡みの存在(蛇の類)との確執]の問題が関わってくる]
とのことの出典を直下、挙げておくこととする。
まずもって、ギルガメシュが[蛇に不死を約する若返りの草を奪い取られた]との碑文上の記載が再発見されたとのことがあるわけだが、についての出典としてはここまでに挙げてきた文書ら内容を参照されたい(出典(Source)紹介の部60にて Penguin Classics版の THE EPIC OF GILGAMESH A NEW TRANSLATIONの Tablet XI.
Immortality Denied(第11碑文要約、[拒否されし不死])の部よりの抜粋として Uta-napishti's wife counsels
him to give the departing hero the customary present for his journey. Uta-napishti tells Gilgamesh how, deep under the sea, a plant-like coral
grows that has the property of rejuvenation. Gilgamesh dives to the sea-bed
and retrieves it. He and Ur-shanabi leave for Uruk. Stopping at a welcoming pool, Gilgamesh bathes in its water, and a snake seizes on his inattention to steal the precious 'plant'. Knowing that he will never rediscover the exact spot where he dived, Gilgamesh realizes at last that all his labours have been in vain.
(訳として)「ウトナピシュテムの妻はウトナピシュテムに今まさに出立せんとしている英雄に旅立ちに際しての慣習上の贈答をなすように助言、ために、ウトナピシュテムはギルガメシュに海の奥深くに[若返りの性質を有する草木のような珊瑚]がいかにして生成を見ているかを伝える。ギルガシュは海底に向けて飛び込み、それを回収する。そのうえでギルガメシュとウルシャナビ(船頭)はウルクに向け出立する。道中、ギルガメシュは心地よさそうな水場を発見、その水につかることとした折、一匹の蛇が彼の意表を突くかたちでかけがえのない[草]を掠め取った。自身が素潜りした海底にあっての(不死の材が生ずる)正確な場を決して再度発見することができないとのことを悟り、ギルガメシュは結局、彼の努力が水泡に帰したことを悟る」といった部よりの引用をなしていたとおりである)。
さらにヘラクレスが黄金の林檎を巡ってラドンという百の頭を持つ竜(蛇のような多頭竜とも)と闘ったとされることについて、下の典拠を引いておく。
(直下、本稿の出典(Source)紹介の部39より引き合いに出しはじめ、度々引用なしてきたところとしてアポロドーロス『ギリシャ神話』(当方所持の文庫版第61刷のもの)p.99-p.102よりの原文引用を「再度」なすとして)

エウルステウスは・・・(中略)・・・第一一番目の仕事としてヘスペリスたちから黄金の林檎を持って来るように命じた。これは一部の人々の言うようにリビアにあるのではなく、ヒュペルボレアス人の国の中のアトラースの上にあったのである。それを大地(ゲー)がヘーラーと結婚したゼウスに与えたのである。
テューポーンとエキドナから生れた不死の百頭竜
がその番をしていた。それとともにヘスペリスたち、すわなちアイグレー、エリュテイア、ヘスペリアー、アレトゥーサが番をしていた。

(引用部はここまでとする ―※― )
(※上に見る[不死の百頭竜たるラドン]については英文Wikipedia[Ladon (mythology)]項目にて Ladon was the serpent-like dragon that twined and twisted around the tree in the Garden of the Hesperides and guarded the golden apples. He was overcome by Heracles.
(訳として)「ラドンはヘスペリデスの園にての樹木に巻き絡みついていたとの[蛇のような竜]となり、黄金の林檎を守護していた。彼はヘラクレスによって打ち負かされた」と端的に表記されているような存在、「半ば蛇」としての竜となる。ちなみに、[竜]にまつわる言い伝えが初期、[蛇](次いで[蜥蜴])にまつわる伝説と近接していたと「されている」ことについても本稿の先の段で若干ながら筆を割いていた。たとえば、オンライン上にての青空文庫サイト(和製版
Project Gutenbergとしての著作権喪失著作を公開しているサイト)でダウンロード可能であるとの「国内では」古今にあって並ぶ者なき博識人と評されていたところの南方熊楠の手になる著作『十二支考
04 蛇に関する民俗と伝説』(岩波文庫)より次のような記述を引いたりしながら、同じくものことについて若干ながら筆を割きもしていた次第である。(『十二支考
04 蛇に関する民俗と伝説』より再度の引用をなすところとして)故にフィリップやクックが竜は蛇ばかりから生じたように説いたは大分粗漏ありて、実は諸国に多く実在する蜥蜴群が蛇に似て足あるなり、これを蛇より出て蛇に優まされる者とし、あるいは蜥蜴やがくが蛇同様霊異な事多きより蛇とは別にこれを崇拝したから、竜てふ想像物を生じた例も多く、それが後に蛇崇拝と混合してますます竜譚が多くまた複雑になったであろう
(引用部終端/ここでは豊富・浩瀚なる読書量に支えられてのことが一目にてうかがい知れる熊楠の例証の類は割愛する))
また、ヘラクレスが追い求めた同じくもの[黄金の林檎]については[エデンの林檎による誘惑の物語]をも介して爬虫類の蛇とつながっていると述べられることがあり、については、本稿のここに至るまでの内容にて十全に指し示してきたとの認識がこの身、筆者にはある(であるから、疑わしきにおかれてはエデンの林檎と黄金の林檎の同質性を論じているとの本稿にての先の段の内容を確認されたい)。
上をもってして
4.[ギルガメシュおよびヘラクレスの特定の冒険にての冒険取得目標物 ――それぞれ洪水伝承と結びつく要素を伴っている[不死の草]と[黄金の林檎]―― に[爬虫類絡みの存在(蛇の類)との確執]の問題が関わってくる]
とのことの出典を挙げたことになる。
以上、ここまででもってして特定の冒険ら([ギルガメシュ叙事詩の今日に伝わる第11碑文(タブレットXIと考古学者に振られての碑文)に見る不死を求めての冒険]および[ヘラクレスの第11功業における黄金の林檎を求めての冒険])にあって
1.[ギルガメシュとヘラクレスが(特定の冒険にて)それぞれ同じくも「大洋を渡って」[地の果て]に赴いた ―大洋の先にあっての辺土に赴いた― と述べられること]
2.[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険対象地に[洪水伝承]と結びつくとの側面を伴っていること]
3.[ギルガメシュとヘラクレスの(特定の冒険にての)取得目標物に不死と結びつくとの側面が伴っていること]
4.[ギルガメシュ・ヘラクレスの(特定の冒険にての)冒険目標物を巡って爬虫類の存在との衝突が生じているとの側面が伴っていること]
との類似性が複合的にみとめられることの典拠紹介を終える。
[ギルガメシュ・ヘラクレスの一致性問題についての補足として]
英文ウィキペディアにも長々とした同男にまつわっての一項目が設けられているとの人物、イングランドにてオガム文字(古代アイルランド文字)の権威・小説家・評論家といった顔を持ち、多才なる知識人として担がれることが多かったとのロバート・グレイヴズという主流派・権威筋の論客(前世紀70年代まで活動の論客)がその著書、
The Greek Myths (日本でも紀伊國屋書店から[権威の外套]を羽織っているとの装丁での訳書が出されている『ギリシャ神話』との書)
にあって
[ギルガメシュとヘラクレスの一致性問題]
について持説を披露しているとのことがあるのだが、そちら比較的目立つところのロバート・グレイヴズ言い様は却(かえ)って、ギルガメシュとヘラクレスの両者の間に一致性があると看做す見方を[信憑性足りぬ言い分]に貶めるようなやりようとなっているとのことがある(:残念だが、著名人による褒め殺しがなされているような格好となってしまっている、としてもいい)。
いかようにしてか。
ロバート・グレイヴズ申しようにあっては(どうして目立つ著名人がそうした見解を披露する必要があったのか理解に失するが)
[こじつげましき側面]
にして、
[正しさに欠けるところの側面]
が目立つようになっているのである。
などと述べても、具体的文言に依拠しての解説をなさないとご納得いただけなかろうから、[反面教師]として目立つところのロバート・グレイヴズ申しようを下に引いておくこととする ――※[文献的事実]を問題としないかたちにて権威サイドの知識人が古典に対する行き過ぎた推論をなしている、そういったありように際会した際に『何故、こういうオーソドックスなことに言及しないで、こういった凝った、なおかつ、的外れな推論が出てくるのか』といった心証を覚えることが筆者なぞには往々にしてあるが、下にて[参考にできぬ、不適切な例]として紹介するロバート・グレーヴズの著者の記述などによって[ギルガメシュとヘラクレスの結びつきを指摘すること]が同文の式でのやりよう、[こじつけがましきやりよう]と見られてしまうとの余地を残したくはない、可及的に残したくはないと筆者はとらえもしている―― 。
(直下、far-fetched(こじつけがましく)かつinvalid(不適切)な申しようとしての Robert Gravesの手になる The Greek Myths ―1960年版.現行、オンライン上よりダウンロードできるようにされているとの著作― よりの引用をなすとして)
It may be assumed that the central story of Heracles was an early variant of the Babylonian Gilgamesh epic which reached Greece by way of Phoenicia. Gilgamesh has Enkidu for his beloved comrade, Heracles has Iolaus. Gilgamesh is undone by his love for the goddess Ishtar, Heracles by his love for Deianeira. Both are of divine parentage. Both harrow Hell. Both kill lions and overcome divine bulls; and when sailing to the Western Isle Heracles, like Gilgamesh, uses his garment for a sail. Heracles finds the magic herb of immortality as Gilgamesh does, and is similarly connected with the progress of the sun around the Zodiac.
(訳として)
「ヘラクレスの冒険譚の中心部はフェニキアを通じてギリシャに伝播していたと考えられる[より昔に遡ってのギルガメシュ叙事詩の変種]と考えてもよいかもしれない。ギルガメシュは親愛なる同志といった按配のエンキドゥを伴っており、ヘラクレスはイオラーオスを伴っていた。ギルガメシュは女神イシュタルに対する愛情ゆえに破滅undoneさせられ、ヘラクレスはデイアネイラに対する愛情がゆえにそうなった(訳注:ヘラクレスはデイラネイアという自身の妻の愚計が原因で毒に塗れて死亡することになったと伝わる存在となっている)。両者ともども神を親に持つ存在である。両者ともども地獄の領域に鍬を入れるがごとくことをなした。両者ともどもライオンらを殺傷し、聖なる牡牛に打ち勝った。そして、ヘラクレスが西の島に船出したとき、彼はギルガメシュのように己が扮装を利用した。ヘラクレスはギルガメシュがそうしたように不死の魔法の霊薬を発見したし、両者の間には黄道十二宮を巡る太陽の進行形態と結びつくとの相似性がある」
(訳を付しての引用部はここまでとする)
「不適切な例」として引いているとの上の部についてはまずもって、
[ギルガメシュがイシュタル神に対する愛ゆえに破滅(ないし人格荒廃)させられた Gilgamesh is undone by his love
for the goddess Ishtar]
というのは[およそ[文献的事実]に合致していない( without philological evidences )]あるいは[的外れな比較をなしている]との意で誇張を伴っての記載(不適切なる記載)となる。
(:ギルガメシュは女神イシュタルの求愛を拒んだために神から攻撃されたもののそれを「斥けた」との存在となっており(たかだかもの英文Wikipedia[Ishtar]項目なぞにて She(Ishtar)
asks the hero Gilgamesh to marry her, but he refuses, citing the fate that
has befallen all her many lovers
と表記されているとおりである)、イシュタルの愛ゆえにの破滅とのニュアンスをそこに認めるのは困難である ――イシュタルの求愛を拒んだために[天の牡牛]がギルガメシュ討伐に送られた、そして、ギルガメシュと友人エンキドゥがそれを斥けたとの記述は和文ウィキペディア[ギルガメシュ]項目の如きものにも記載されているとおりではあるが、筆者は同文のことにまつわるギルガメシュ叙事詩の英文解説書籍・論稿らをも検証しており(それら資料名らも本稿にて挙げている)、そこよりイシュタルの愛が原因でギルガメシュが[破滅]したとの記述は全く見受けられないことを把握している―― 。但し、undoneとのロバート・グレイヴスの(引用テキストに見る)言いまわしを[破滅させられた]としてではなく[人格荒廃させられた]との意でとらえれば、[イシュタルの愛が原因でギルガメシュがその友人エンキドゥを亡き者にさせられ、結果的に人格荒廃を見ることになった](本稿にて先述のこととなる)との式でそこに妥当性があるように「見え」もするのだが [人格荒廃を見た]ことと[ヘラクレスがその妻デイラネイアの愛が原因で「死亡」とのかたちで破滅undoneさせられた]が如くことを並列して比較することは比較方式として妥当なやりようとはならない([人格荒廃]と[死亡]は類義のこととならない)。すなわち、ロバート・グレーヴズのその部にてのいいようは何れにせよ妥当な物言い「ではない」)。
また、同じくものロバート・グレーヴズ著作にあっての抜粋部に認められる、
[ギルガメシュは親愛なる同志といった按配のエンキドゥを伴っており、ヘラクレスはイオラーオスを伴っていた Gilgamesh has Enkidu for his beloved comrade, Heracles has Iolaus]
という著者申しようからして実にもってfar-fetched[こじつけがましきもの]である。
(:ここまででもその点について古典内記述を引いて示してきたようにエンキドゥは[ギルガメシュの運命そのものを変えた莫逆の友]との描写のされ方の存在となっている。対してヘラクレスの従者イオラーオス(ヘラクレスの双子の兄弟の息子)については[ヘラクレスの冒険に時たま助力していると描写がなされている程度の存在]となっており、また、エンキドゥがそのような存在として描かれているように[物語の次なる展開につながる重要な役割を担った者]でもなければ、物語主人公より先に死亡してもおらず(ギルガメシュ叙事詩ではギルガメシュより先にエンキドゥは死亡している)、同イオラーオス、ヘラクレスよりも長生きしている。
従って、ヘラクレスの旅の道連れイオラーオスとギルガメシュの旅の道連れエンキドゥを対置させて挙げるが如く挙は[物語の脇役としての目立たぬ従者]と[物語の主要登場人物としての主人公の無二の親友]を同様の重み付けが与えられた存在として挙げるが如く挙に等しい(重み付けに対する顧慮もなせぬ・なさぬとの頭の具合のよろしくはないやりようないし「どうせ何も分かっていないのだから」と読み手の無知につけ込んでの性質悪きやりようでもいい)
ロバート・グレーヴズ Robert Gravesについては ――同男がいかに[「これぞ権威」と担がれていた知識人]であったとしても―― そのようにほとんどつながらないもの(エンキドゥとイオラーオス)を結び付けているがゆえに「も」性質が悪い向きと解されるわけだが、といったロバート・グレイヴズの主張内容だけを(グレイヴズ本人の具体名すら挙げずに)批判する、ギルガメシュとヘラクレスの結びつきを問題視することを同じくもの論法で批判する英文ページもがオンライン上にあって目に付くとのことがある(すぐ後にて具体例紹介する)。ロバート・グレイブヴズの悪辣性に気付いているというのか、あるいは同男がはなから
[特定の観念を否定するためにわざと負けるべくも用意された闘犬にての「弱い犬」](目立つように用意された噛ませ犬、アンダードッグUnderdog)
[ユースフル・イディオット](矛盾を胚胎しての問題ある社会システムの維持にとり都合の良いことしか言わぬ、ないしは、本質から見ればどうでもいいような下らぬことをそれが「さも重要なること」であるように目立って論じたてるとの類が[虚名]を与えられて重宝がられているとのケースにての[露出する(自称・他称の)識者]を、そうも、ユースフル・イディオット「役に立つ愚者」と表することもある)
のような者として世を渡っていた(そういう類はテレビを点ければ、いや、ありとあらゆる教育現場や説教の現場などですぐに目に入るわけだが、とにかくも、のような者として世を渡っていた)とのこともがありうる中で、そうした人間を[運用]する意向に沿って[弱い犬]を間接的に攻撃する動機でもあったのか、ロバート・グレーヴズそのもの「ではなく」同男主張内容と同じくものことを目立って否定するが如く英文ページがオンライン上にて目につくようになっているとのことがあるのである(ロバート・グレーヴズの名を明示的に挙げずに同男の不適切なる主張の中身を叩き、「ギルガメシュとヘラクレスの一致性を問題視するのはこじつけがましいことである」ように述べているとの英文オンラインページ「も」どういうわけなのか目につくとのことがある)。
オンライン上にて ――[ギルガメシュGilgamesh]と[ヘラクレスHercules]の両者名称を双方英文入力して検索すると現行目立つように表示されてくる質問・回答形式ページとして―― 、
[ヘラクレスとギルガメシュの類似性につき「なぜなのか」問いあわせているとの質問に回答するとの[体裁]にてのメジャーどころの英文質問サイト]
の内容が「現行」、目につくとのことがあり、の中では、
「ギルガメシュとヘラクレスの[冒険の相棒]を介したつながりはない」
といった[普通に考えれば、日常生きるうえでは問題視する必要「もない」こと]を意図不明に挙げ連ねての回答者回答が「わざわざ」なされていたりもするのである ――※そうしたページの残置残存に関してはなんら請け合えないが、すくなくとも本稿執筆時現行にては What is a difference between gilgamesh and hercules?「ギルガメシュとヘラクレスの相違点は?」との質問が Yahoo! Answers(日本にて質問者質問に回答を与えているYahoo知恵袋の海外版)の Web siteに挙げられ、そちらが[ギルガメシュ][ヘラクレス]の複合検索にての検索エンジン検索にて目につくようになっている中で、 Gilgamesh had a best friend and companion who shared his adventures; Hercules
had several companions but no long-term, exclusive one.
「ギルガメシュは彼と冒険を共にした無二の共にして道連れを伴っていたが、ヘラクレスについては複数の旅の道連れを伴っていた中でただ一人を除いて長期の連れはいなかった」などとの表記が回答者によってなされ、[(重要ながらその同定・捕捉にはある程度の知識が要されるとの際立っての一致性問題が捨て置かれたうえでの)相違点ばかりを挙げ連ねるとの式での論法]より導き出されている[ギルガメシュとヘラクレスの物語は結びつかないとの帰結]が強くも前面に押し出されているとのことが見受けられるようになっている(繰り返すが、ギルガメシュとヘラクレスとの両語をもってして Search Engineを動かすことで出てくるサイトにてそういう言い分・言いようがなされている)。につき、筆者なぞは『 Robert Graves(の死骸の皮の如くもの)なぞを不適切なること甚だしくもの[Underdog](闘犬にての弱い犬)として[運用]すればそういう物言いもなせよう』と解している―― )。
この世界で目立つ[知識人]、(故)ロバート・グレイヴズのやりようとのことでさらに述べれば、
[ヘラクレス本人が不死の霊薬としての若草を発見した Heracles finds the magic herb of immortality
as Gilgamesh does.
(先にての引用部を参照のこと)
などという Robert Graves書きようは[誤り](incorrect)、すくなくとも、[文献的事実ではない]( without philological evidences )であるためにそのようなことをヘラクレス・ギルガメシュの一致性の問題の論拠として持ち出しているのは良くて「不適切」、悪くて「論外」であると考えられるとのこともある ――ただし、同じくもの点に関してはヘラクレスが乞い求めたゴールデン・アップルにあっての北欧神話などに見る「不老不死を約する果実」との特質と結びつけて見れば、話は別である―― 。
「さらに」に「さらに」を加えてのくどくもの話をなせば、ロバート・グレーヴズがギルガメシュとヘラクレスが黄道十二宮にあっての[太陽の運行]と双方結びつく存在であるように(先にて引用なした部で)書き記していることも不穏当であると受け取れるようなところがある(はきと不穏当であるとは断じられないものの、である)。ヘラクレス12功業が黄道十二宮のいくつかの星座の由来として言及されていることがあっても(殊に[蟹座]や[獅子座]や[射手座]の由来はヘラクレスの12功業の中にて求められてもいる)[ギルガメシュ神話と共通のもの]として両雄「ともども」が太陽の運行と結びつくとの申しようが深くも理に適った式でなされているのか、とのことについては判断が難しく首をかしげざるをえないところであろうととらえられるようになっているのである。
(:以上のことすべてを顧慮したうえでのこととして「権威筋の」よく知られた論客 ――日本では紀伊國屋書店などがさも[一級の知識人]であるようにそのギリシャ神話関連の書籍の邦訳版を刊行しているとのロバート・グレーヴズ―― に由来する[悪質なやりよう]であるととらえている。
それにつき、
「世間にては
[論証したきことがまず先にあってその論証したきことを適正・十二分に指し示すためにそれをなす]
という、
[本来そうあるべきかたちでの[引用]]
をなす、そういうことすらも満足に出来ないとの人間が多い」(なかんずく[本来的には空虚なるものに過ぎぬ紛い物]が[有識者][思考力ある人間]の「フリ」をしているとの[双方の類]らのやりように関して述べれば、[引用]がなされていてもそこに脈絡が何らない、なぜ、どうして引用をなしているのか、引用をなす必要もないところで[引用]がなされながら結局、[無意味・無価値なる属人的印象論]が導出されるだけに終わっている ([引用]でもって「自慢高慢馬鹿のうち」といった程度の浅薄なる知識でもひけらかしたいのか、あるいは、[隙間を埋めるべくもの間に合わせ存在][アンダードッグ]ながらもの存在自体を目立つように前面に押し出す意図でもあるのか、といった按配での[本当に何かの建設的作用をきたす可能性]が伴っていない ――[立証][論証]でもなければ無論、[告発]ですらない―― との[無意味・無価値なる属人的なる印象論]に終わっている) といった側面すらもが見受けられる)
とのことがありもするなかで
「ましてや、引用なす者にあってはその引用の元とすべきか検討の俎上に載せての学者の申しようが正しいか正しくはないかとのことを引用対象史料の検証までなして分析する人間に至ってはよりもって少ない」
とのことがあると筆者「も」見るに至っている(そういうことを大学時代の教授の慨嘆の言として聞いたことがある。その教授は暗に「権威の外套を纏(まと)う学者とて平然と偽りをなす」と述べたかったのかもしれないが)。
そうした見方をなしている人間として「強くも」申し述べておくが、
「本稿にあっての筆者の[引用]に対するスタンスは
[引用をなす際には引用元が[権威]由来のものであるかどうかの別なくその正確性に注意を払っており、自身が論証したきことを「適正に」指し示すことに最深の注意を払っている]
とのものである」
とのこと、よくご理解いただき、是非とも、その通りか否かの批判的検討を請いたいものである ――それにつき、筆者とて[過度に憶説がかっての内容を有しての文物][多くの誤りを胚胎している(と見立てている)文物]より引用をなすこともあるわけだが、そういうことをなす場合には「それが世間から相応の評価を受けているものですよ」「こういう誤り・欠陥を伴っていますよ」と断りつつもの引用ないし内容紹介をなすことにしており、そうもしつつの引用をなしている場合は『劣悪なるものから取り合うに値する部分を抽出(救出)できる』と考えているケース、ないしは、「こういう視点すらもがある」「欠陥性それそのものが問題になる」とのその材料呈示のために留めてのケースに限られる(本稿の「批判的」内容確認でもってして読み手となる向き自身でご確認いただきたいのだが本稿にて筆者には[適正さ]を指向する確固たる意図がある)。 対して、である。[相応の類ら]はサブ・プライム問題(金融危機)を引き起こした住宅ローン担保証券流通システムに見る「ような」やりよう(サブ・プライム・ローンのといった側面につきご存知なければ『インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実』とのドキュメンタリー映画を見ているとよい)、[劣悪なるもの](正当なる裏付けがないもの)と[正しいもの](正当なる裏付けがあるもの)を[不正確な、あてにならぬ基準]でもって混ぜあわせる、責任感もなんらないとの式で両者を十把一絡げに混ぜあわせるとのことをなし、[周囲(広くも見れば世間)に害しか及ぼさぬとの紛い物]を構築するようなことばかりをなしていると見受けられる。心ある読み手にあっては世の中に充満しているそうもした紛い物に惑わされず正しい道を道究めてもらいたいものである (読み手が行為動態に対する前もっての目分量さえ有しておれば、そう、[機械のような存在](運命を与えられるだけの存在)としてではなく[思考なせる人間](運命を切り拓かんとする者)として同じくもの視点で[対象]を注視するだけの前もっての目分量さえ有しておれば、本来ならば、[相応の存在]を見極めることができ、紛い物なぞに騙されることもないだろうとも筆者は思ってもいるからそうも強くも申し述べている(ただ、そうしたことは万人に期待できることではないともあわせて見ている。そも、我々人間の世界では賢愚の別も甚だしく、また、魂の抜けきった木偶のような者らで満ちた我々人間の世界では[理]も[知]もない宗教ドグマに嵌まっているないし嵌まっている振りをしているが如き者らが(諺に曰くの)「固まり法華に徒党門徒.」とのマス・ゲーム式で[理]と[知]の領域を「彼らの」都合で破壊しようとしている様も目に付く、であるから、同じくものことを万人に期待できるはずもなかろうと見ているわけである。しかし、であっても、[生き残るためにあがく]、すなわち、[死地から抜け出んとするだけの潜在力を有している]との向きらのためにものしている本稿にあってはそのような注記を敢えてもなしている)―― )
(ロバート・グレーヴズ『ギリシャ神話』を引き合いに出してのギルガメシュ・ヘラクレスの一致性問題についての補足はここまでとする)
(極めて長くもなったが、出典(Source)紹介の部63(3)はここまでとする)
直近直上の部までにて典拠示してきたようにギルガメシュとヘラクレスの冒険譚の間には
[大洋を渡っての辺土 ―地の果てといった辺土― に向けての冒険との側面]
[冒険目的地が洪水伝承と結びつくこととなっているとの側面]
[冒険にての取得目標物(ギルガメシュ:不死の草、ヘラクレス:黄金の林檎)が[不死]と結びつくとの側面]
[冒険取得物にまつわり[爬虫類の存在(蛇と接合する存在)との確執]との要素が関わってくるとの側面]
との共通性が見てとれるとのことがある。
はきと述べるが、双方ともに「獅子と結びつく形で偶像化されてきた(獅子を御し、獅子の皮をまとった姿にて偶像化されてきた)」存在にして、双方ともに「半神(デミゴッド)との属性を有している」存在らにあっての特定の旅の物語 ――片方は伝説の大洪水の生き残りウトナピシュテムを探し求めてのギルガメシュの旅の物語、片方は(かのアトランティスと同一視されてきた)黄金の林檎の園を求めてのヘラクレスの旅の物語―― にあって、
[大洋を渡っての辺土 ―「地の果て」といった辺土― に向けての旅との側面]
[旅の目的地が洪水伝承と結びつくこととなっているとの側面]
[旅にての取得目標(ギルガメシュ:不死の草、ヘラクレス:黄金の林檎)が[不死]と結びつくとの側面]
[取得目標にまつわり[爬虫類の存在(蛇と接合する存在)との確執]との要素が関わってくるとの側面]
との一致性が(くどいが、それぞれ一単位の特定の冒険の間にて)具現化を見ていることをして
[ただの偶然の一致である]
などと決めつけるのはあまりにも愚かなやりようであると明言したい次第である(言い方を換えれば、ここまで述べてきたような多重的一致性があるところにて偶然である云々といった申しようをなすのは「正気ではない」といった具合に頭の具合がよろしくはないことであると明言したい次第である;おかしいことを言っているつもりはない。要するに[明示的に指し示されるところの多重的一致性]から何らかの事情あってギルガメシュ・ヘラクレスの両者の物語は結びつくようになっていると明言したいのである。 それにつき、――先の段にて言及したことを再言及するとして―― [ギルガメシュが不死を求めてウトナピシュテムの地に旅立つ原因(エンキドゥの死)をそもそものところとしてもたらした]のがイシュタルという女神となっており、彼女イシュタルについてはギリシャの女神、[黄金の林檎を是が非でも求めんとしたアフロディテ]と同一視されもする存在、[金星体現存在][美と愛の女神][彫像化の態様](鬚を生やした奇怪なるイシュタル像と鬚を生やした奇怪なるヴィーナス・アフロディテ像との言われようについて先述)とのありようから[黄金の林檎を是が非でも求めんとしたアフロディテ]と同一視されもする存在となっているのこと「も」またある ――あまりにもってよくできているところではある。実に悪い意味で、だが―― )。